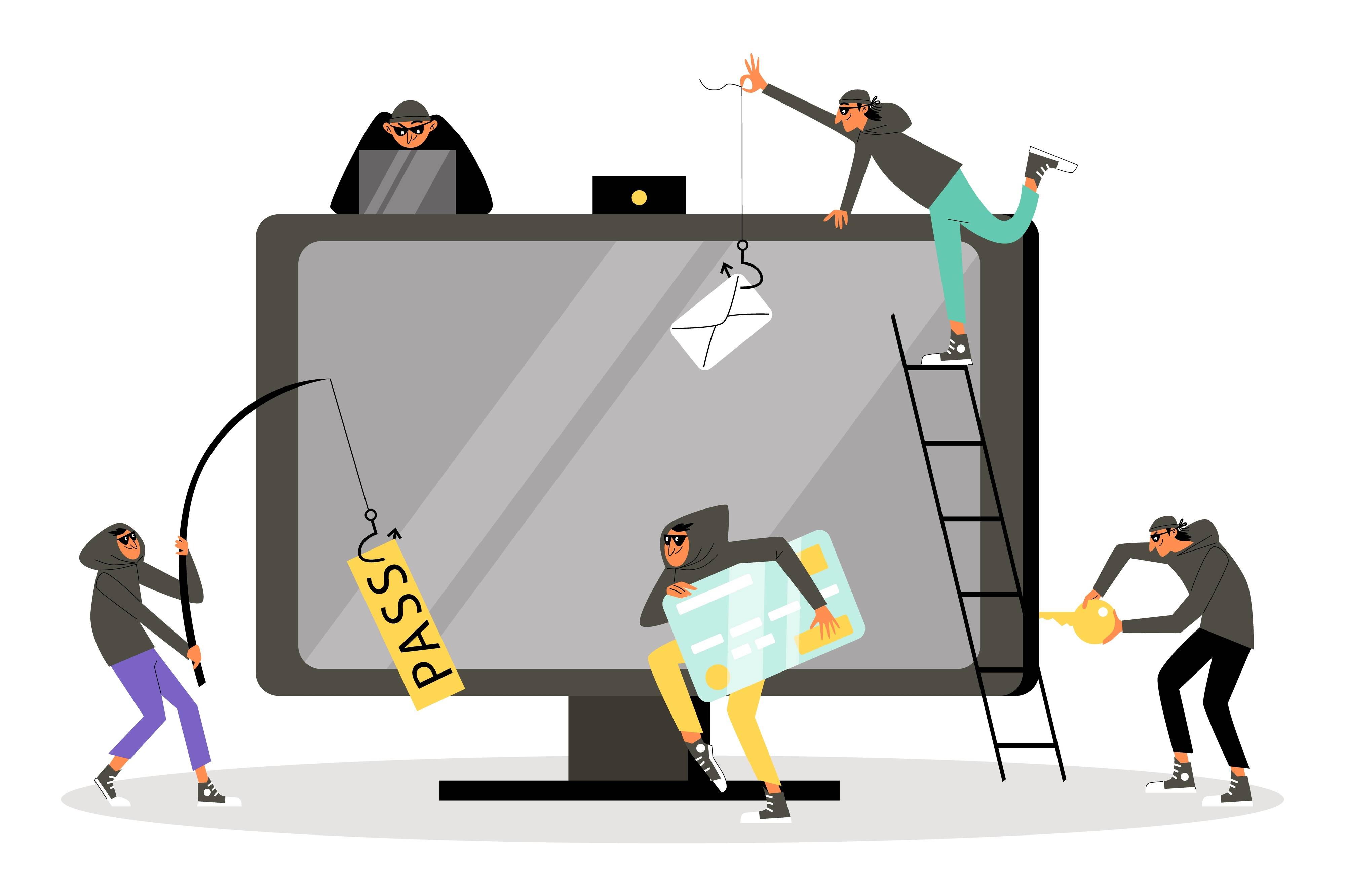怪しいメールはなぜ届く?主な種類や対策法について解説

見覚えのない送信者から、怪しいメール(迷惑メール)が送られてきた経験はないでしょうか。見覚えのない不審なメールが届いた場合、適切に対処しなければトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるため、注意が必要です。
この記事では「怪しいメール(≒迷惑メール)」が届く理由や、注意すべきメールの主な種類、迷惑メールの受信によるリスクを低減させる方法を紹介します。この記事を参考に、迷惑メールのリスクから身を守りましょう。
目次
怪しいメールとは?

怪しいメールとは全く知らない相手から勝手に配信されるメール、または身に覚えのない内容が記載された不審なメールなどを指し、一般的に「迷惑メール」とほぼ同義で扱われています。具体的な例として、主に以下のような種類があります。
| 怪しいメールの主な種類 | 目的 |
|---|---|
| 架空請求メール | 実際には発生していない料金などの請求を行い、金銭を騙し取る |
| フィッシングメール | 金融機関やクレジットカード会社、ECサイト会社などになりすまし、金銭や個人情報を盗み取る |
| ウイルスメール | ウイルスに感染させ、個人情報などを盗み取る |
| 広告宣伝メール | メールの配信に同意していないユーザーに対して、サービスや商品を一方的に宣伝する |
それぞれのメールの詳細な特徴は後述しますが、まずは上記のような種類があることを覚えておくとよいでしょう。
怪しいメール(≒迷惑メール)はなぜ送られてくる?
怪しいメール、つまり迷惑メールはさまざまな目的で送られてきます。ここでは、悪意のある第三者が迷惑メールを送信する目的と、メールが届いてしまう原因について解説します。
迷惑メールを送信する目的は?
迷惑メールの多くは、悪意を持った第三者が受信者の個人情報を収集したり、その情報をもとに金銭を騙し取ったりするために送信されています。たとえば、メールに記載したURLから偽のWebサイトへ誘導し、個人情報やクレジットカード情報などを入力させて情報や金銭を盗み取る手口があります。
また、ウイルスの拡散を目的とするケースも少なくありません。ウイルス感染によって個人情報を盗み取り、盗んだ個人情報を不正に悪用するリスクも想定されます。
迷惑メールが届く原因とは?
迷惑メールが届く主な原因として、Webサービスやアプリなどで登録したメールアドレスが漏洩している可能性が考えられます。
また、ランダムで生成したメールアドレスにメールを自動送信する手法もあるため、自分で情報を入力した覚えがなくても迷惑メールが届くケースもあります。
さらに、SNSで公開しているメールアドレスを自動プログラムで収集しているケースもあります。不特定多数が閲覧できる場でメールアドレスを公開する際は、迷惑メールの受信リスクが高まることを理解しておく必要があります。
主な迷惑メールの種類
迷惑メールには、主に5つの種類があります。これらの怪しいメールに騙されないよう、巧妙化している手法を把握しておくことが大切です。ここでは、各種類について詳しく解説します。
架空請求メール
架空請求メールとは、インフラサービスの料金や有料コンテンツの料金など、本来は発生していない料金が発生しているように見せかけ、金銭を請求するメールです。
怪しいメールの件名や本文には「あなたの資産を差し押さえる」「自宅まで取り立てに行く」などの受信者の不安を煽る文面が書かれている場合が多くあります。不安になった受信者は慌ててATMにお金を振り込みに行ったり、メールに記載のWebサイトにアクセスしてクレジットカード番号を入力してしまいます。これにより、受信者は金銭をだまし取られてしまいます。
フィッシングメール
フィッシングメールとは、金融機関や通販サイト、宅配業者などになりすまし、個人情報や金銭を不正に盗むことを目的としたメールです。メールに記載のURLから偽のWebサイトへアクセスさせ、パスワードやID情報、クレジットカード情報、銀行口座番号などの入力を促します。
一例として、大手の通販サイトを装い「不正にアクセスされた可能性があるため、お支払い情報の変更が必要です」といった文面で個人情報入力を求めてくるケースが挙げられます。メールに記載のURLにアクセスすると巧妙につくられた偽のサイトに遷移し、そこでクレジットカード情報などを入力してしまうことでカードが不正利用され、金銭的な被害に遭うといったケースがあります。
ポルノ詐欺・脅迫詐欺メール
ポルノ詐欺・脅迫詐欺メールとは、2018年頃から流行している迷惑メールの一種で「セクストーションメール」とも呼ばれています。「アダルト系のWebサイトを閲覧している様子を撮影し、連絡先の情報も取得している」といった、人に知られたくないような内容で脅し、金銭を騙し取ろうとします。このような脅し文句の文面により、メールに記載のURLなどにアクセスさせ、クレジットカード情報の入力などを促すことがあります。
また、受信者のスマホハッキングしていることを信じ込ませるため、「マルウェア(スマホやユーザーに被害をもたらすことを目的とした、悪意のあるソフトウェア)に感染しています」「パスワードを把握している」などの脅し文句を使用する場合もあります。
そのほか、「至急の対応が必要です」「48時間以内に支払わないとアダルトサイトの閲覧記録をネット上に拡散します」といったように相手を焦らせ、支払いを急がせる内容もよく見られる手口です。
ウイルスメール
ウイルスメールとは、Webサイトへのアクセスやアプリのインストール、添付ファイルの開封などを誘導し、ウイルスに感染させるメールのことです。なかにはメールを開いただけで感染する場合もあるため、注意が必要です。
ウイルスに感染すると、悪意のある第三者に端末を遠隔操作されるリスクや、それに伴う個人情報漏洩のリスクなども想定されます。
広告宣伝メール
広告宣伝メールとは、サービスや商品を周知するために送信されるメールのことです。ユーザーがメールの配信に同意している場合は、単なる広告宣伝メールとして受信することになります。
しかし、ユーザーが同意した覚えのない広告宣伝メールが届いた場合は、ユーザーにとって迷惑メールだとみなされるでしょう。法律の側面からも、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」では、メルマガ登録などで事前に同意を得た受信者以外にメールを配信してはならないと定められているため、ユーザーが同意していないサービスや商品の広告宣伝メールは「迷惑メール」とみなされます。
加えて、迷惑メールのなかには「メールを開いたことを送信者に知らせるプログラム」が組み込まれているものがあります。サービスや商品の広告宣伝を謳って不特定多数のメールアドレスに配信し、メールの開封によって有効なメールアドレスであることが送信者に知られてしまい、さらに迷惑メールが届くリスクも考えられます。
迷惑メールによるリスクを低減させる方法
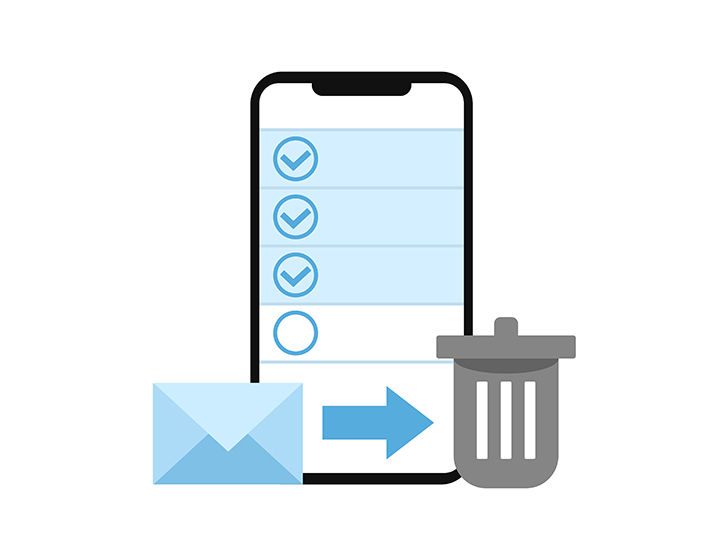
迷惑メールには、さまざまなリスクが潜んでいます。しかし、適切な対処法を知っておくことで、迷惑メールによるリスクを最小限に抑えることが可能です。ここでは、迷惑メールのリスクを低減させる方法を紹介します。
メールを開かず削除する
メールの件名の日本語が不自然である、送信相手に見覚えがないなど、開封前に怪しいと感じたポイントがある場合は開かず削除しましょう。
もしメールを開封してしまうと、前述したように実際に使われているアドレスであることが相手に伝わり、迷惑メールがさらに届く可能性が高まるため、開封しないよう注意してください。
メールに記載されたURLにアクセスしない
迷惑メールと気づかず開封してしまった場合、本文に記載のURLにはアクセスしないように注意しましょう。ウイルスメールなどの例外はありますが、URLにアクセスしなければ、大きな被害につながる心配はほとんどありません。
悪意のある第三者は、実在する企業になりすまして迷惑メールを送信し、本文内のURLにアクセスするように誘導します。アクセス先が個人情報を入力させる悪質なサイトである場合、情報を入力すると個人情報が漏洩したり、ログイン情報やクレジットカード情報などが不正利用される危険性があります。
もし、本文に不自然な日本語が使われている場合や、メールアドレスが小文字の「l(エル)」を「I(アイ)」や「1」に変えて公式のアドレスに似せた不自然な文字列になっている場合など、開封後に不審な点を見つけたら、その時点でメールを削除するのが賢明です。
個人情報を入力しない
怪しいURLにアクセスしてしまっても、個人情報を入力しなければ深刻な被害を回避できる可能性が高まります。個人情報の入力を促すポップアップが表示されることがありますが、無視してブラウザを閉じてください。
メールフィルタリング機能を活用する
メールフィルタリング機能を活用することで、メールを開封せずに不審なメールを判別することが可能です。
ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」には、「迷惑メール対策」機能が備わっています。迷惑メールと判断したメールを自動で振り分け、専用の迷惑メールフォルダに保存してくれます。そのため、リスクのある迷惑メールを開かずに削除することが可能です。
また、電話帳に登録しているメールアドレスからのメールだけを受信する設定もあるため、迷惑メールが届くリスクを低減できるメリットもあります。
まとめ
見覚えのない送信者から怪しいメールが送られてきた場合は、安易に開いてはいけません。詐欺被害のリスクが高まったり、ウイルスに感染する可能性があるため、不審に感じた際は開封せず速やかに削除しましょう。
また、メールフィルタリング機能を持つセキュリティ対策サービスを活用するのもおすすめです。怪しいメールにお悩みの方は、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。