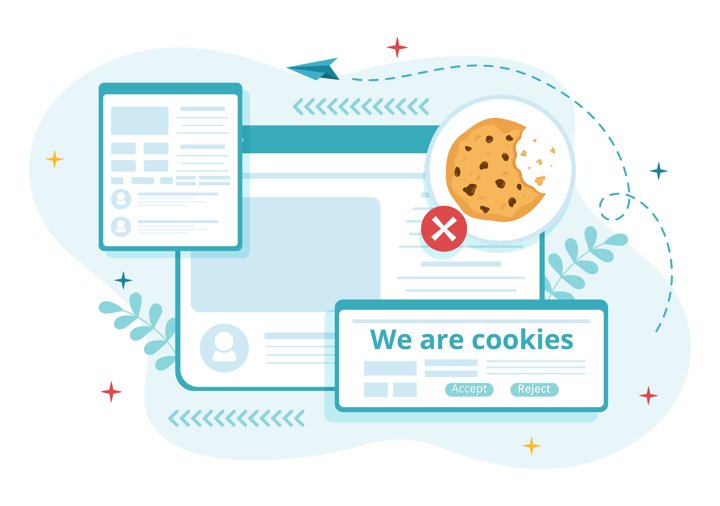電子マネー詐欺から身を守る対策とは?具体的な手口とともに解説

架空請求やフィッシング詐欺、サポート詐欺など、巧妙な手口の詐欺によって多くの人が知らないうちに騙され、金銭を失うケースが後を絶ちません。特に電子マネーの利便性を悪用した詐欺は、短時間で被害が発生しやすく、一度送金してしまうと取り戻すのが困難です。
本記事では、電子マネー詐欺の具体的な手口を詳しく解説するとともに、被害を未然に防ぐための対策を紹介します。
架空請求やフィッシング詐欺、サポート詐欺など、巧妙な手口の詐欺によって多くの人が誘導され、金銭を失うケースが後を絶ちません。
本記事では、電子マネー詐欺の具体的な手口を詳しく解説するとともに、被害を未然に防ぐための対策を紹介します。
目次
電子マネーを用いる詐欺の手口

電子マネーを利用した詐欺は、手軽に送金できる仕組みを悪用した手口の一つです。ここでは、電子マネーを用いる代表的な詐欺の手口を紹介します。
架空料金請求詐欺
架空料金請求詐欺は、実際には利用していないサービスの未納料金や利用料を請求する手口です。悪意ある人たちはメールやSMS、電話を使い、被害者に対して「有料サイトの料金が未納になっている」「支払わなければ裁判を起こす」などと脅します。
そして支払い方法に電子マネー(ギフトカードなど)を指定し、購入と番号の送信を求めてきます。詳しくは次の記事を参考にしてください。
ワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺とは、Webサイトやメールなどに記載されたURLにアクセスしただけで一方的に契約が成立したという画面が表示され、電子マネーなどで高額な料金を請求される詐欺のことです。
料金請求の際にはスマホやパソコンの識別番号、利用しているインターネットサービスプロバイダの情報などを表示させることで、ターゲットの個人情報を特定しているかのように装い、不安を煽ってきます。
また、期限内に支払わない場合は「延滞料が加算される」「法的措置を行う」といった脅迫的な内容で、利用者に支払いを迫る手口が特徴です。
サポート詐欺
サポート詐欺は、ユーザーの不安を煽ることで金銭を騙し取る手口です。スマホやパソコンの画面に「ウイルスに感染しています」「すぐに対応しなければデータが消失します」といった警告を表示させたり、突然警告音を鳴らしたりすることで、ユーザーに不安を与えます。
そして、画面に記載された「サポート窓口」に電話をかけさせ、偽のサポート担当者が対応します。ターゲットが指示に従うと、「ウイルス除去のための費用」として電子マネーの購入を求められます。
なりすまし詐欺
なりすまし詐欺は、悪意ある人たちが被害者の知人や家族になりすまして電子マネーを騙し取る手口です。具体的には、被害者の知人や家族のLINEやSNSアカウントを乗っ取り、メッセージを送信します。
「急にお金が必要になった」「電子マネーを購入して番号を教えてほしい」などと依頼し、ターゲットを騙します。メッセージは普段のやりとりと似た口調で送られてくるため、違和感を持ちにくいことが特徴です。そのため、不審なメッセージを受け取った際には、別の手段で本人に直接確認することが求められます。
QRコード詐欺
QRコード詐欺は、店舗に掲示されている正規のQRコードに偽のQRコードを上から貼り付け、利用者が誤って読み取るように仕向ける手口です。利用者が気づかずに偽のQRコードを読み取ると、店舗ではない別の口座に直接送金される仕組みになっています。
主に被害の対象となるのは店舗ですが、利用者もトラブルに巻き込まれる可能性があるため、注意が必要です。QRコードを利用する際は、貼り替えられた形跡がないか、不自然なデザインやフォントの違いがないかを確認し、少しでも違和感があれば店員に報告することが大切です。
電子マネー詐欺を防ぐための対策

電子マネーを利用した詐欺の手口は巧妙化しており、巧みに誘導されて被害に遭うケースが増えています。被害を防ぐためには、詐欺の手口を理解することに加え、セキュリティ対策や冷静な対応が大切です。
ここでは、電子マネー詐欺を防ぐための具体的な対策を紹介します。
セキュリティ対策サービスを活用する
電子マネー詐欺のリスクを減らすために、セキュリティ対策サービスを利用するのも有効です。電子マネーを悪用した詐欺の手口には、不審なサイトに誘導するものや、被害者の不安を煽るような電話をかけてくるものがあります。
こうした詐欺を未然に防ぐために、ドコモが提供する「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」のようなサービスを活用するのも有効です。たとえば、同プランで利用できる「危険サイト対策」機能であれば、閲覧しようとしているサイトがワンクリック詐欺やサポート詐欺を行うような危険なサイトだった場合に、警告画面が表示されます。
このようなサービスを活用することで、不審なサイトにアクセスするリスクを軽減できるでしょう。
突然ブラウザ上に不審な警告画面が表示されても無視する
サポート詐欺の多くは、偽のセキュリティ警告画面を使って被害者を誘導します。突然ブラウザに「ウイルスに感染しました」「PCが危険な状態です」といった警告が表示されても、慌てずに冷静に対応することが重要です。
特に、警告画面にサポート窓口の電話番号が表示されていても、絶対に電話をかけないようにしましょう。もしも誤って電話をしてしまい、相手から電子マネーでの支払いを求められても、決して指示に従わないでください。
警告画面の適切な消し方については、次の記事で詳しく解説しています。
サポート詐欺の偽広告画面の消し方とは?詐欺被害に遭った場合の対処法
料金の支払いを促す不審なメールに応じない
「有料動画サイトの料金が未払いです」「本日中に連絡がない場合は法的手続きに移行します」「コンビニで○○ギフトカードを購入してください」といった内容のメールが届いた場合、架空請求詐欺の可能性が高いです。実際に、電子マネーでの支払いを求められ、詐欺被害に遭うケースが発生しています。
そのため、不審なメールを受け取った場合は記載されているURLにアクセスせず、直接公式サイトにアクセスして確認するか、公式の問い合わせ窓口に連絡して内容の真偽を確かめることが重要です。また、こうした詐欺メールを未然に防ぐために、セキュリティ対策を強化することも有効です。
まとめ
電子マネーを利用した詐欺は、架空料金請求詐欺やフィッシング詐欺、サポート詐欺など、さまざまな手口で行われています。悪意ある人たちは被害者の不安を煽ったり、正規の企業を装ったりして巧妙に金銭を騙し取ろうとするため、詐欺の手口を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
また、被害を防ぐためにもセキュリティ対策サービスを活用し、不審なサイトや電話への対策をするのもおすすめです。電子マネーを使った詐欺の被害を未然に防ぐためにも、この機会に導入してみてはいかがでしょうか。