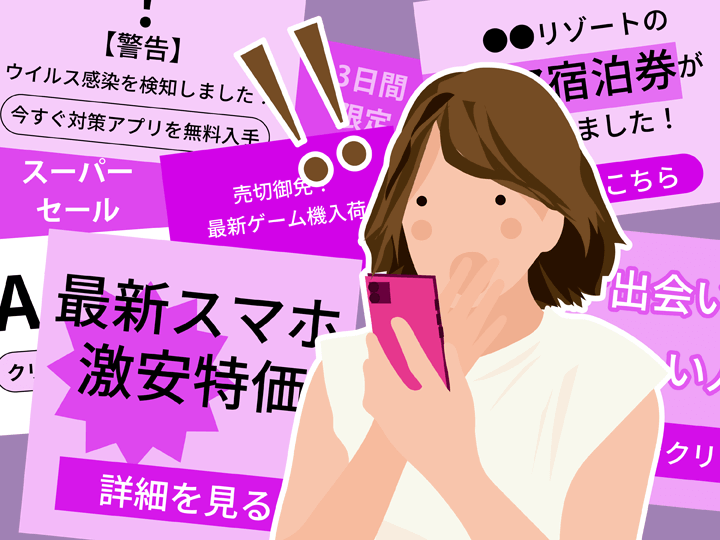詐欺メールを開いてしまったらどうなる?対処法や詐欺メールの見分け方を紹介
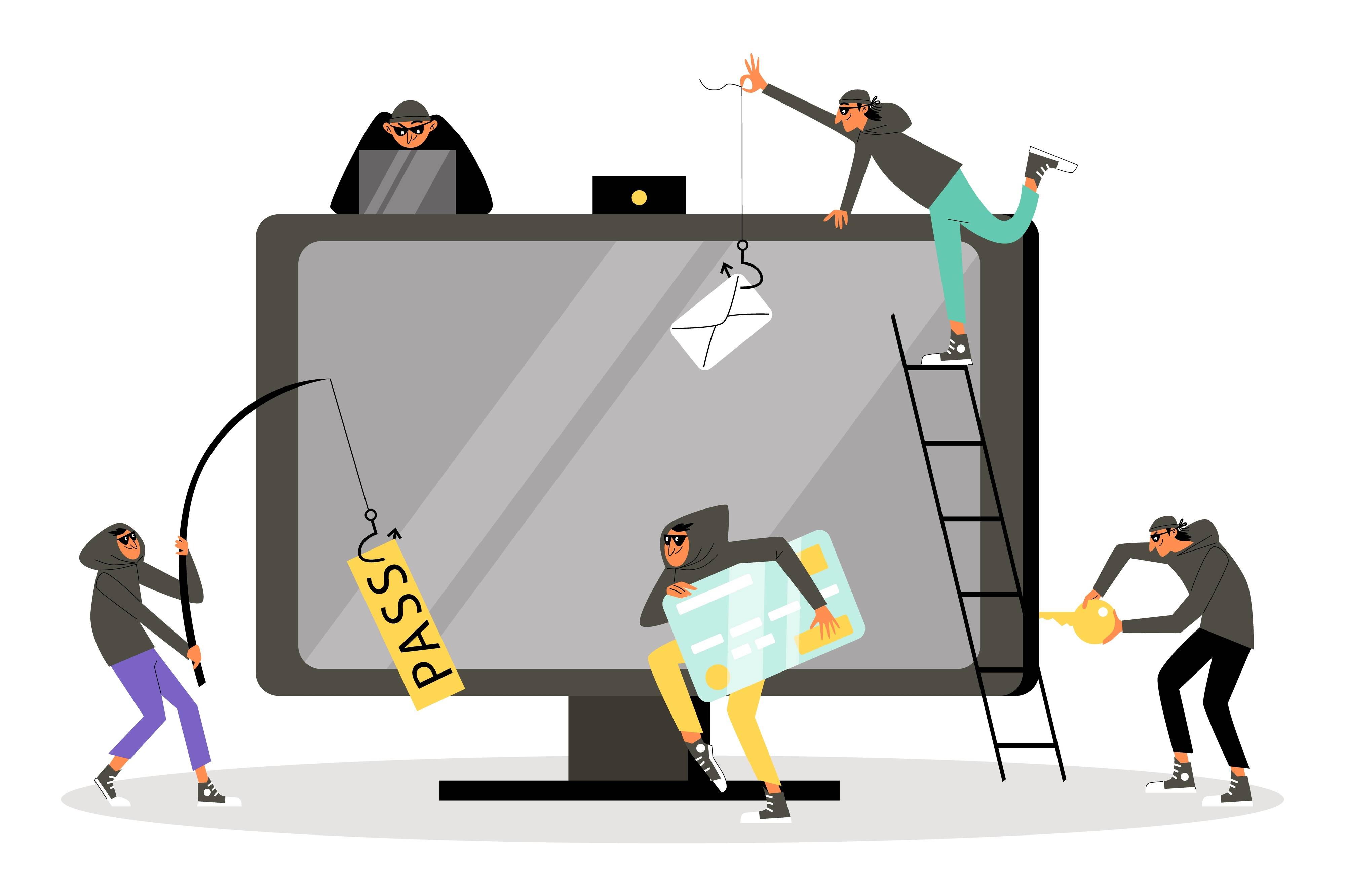
メールボックスを開くと、怪しげな件名のメールが届いていた経験はないでしょうか。そのようなメールのなかには、詐欺目的で送られてくるものもあります。誤って開いてしまい、どのような危険があるのか不安に感じる人もいるでしょう。
この記事では、詐欺メールを開いてしまった場合の影響や、適切な対処法について解説します。また、詐欺メールの見分け方や予防策についても詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
詐欺メールを開いてしまったらどうなる?

詐欺メールを開いてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?以下、想定されるリスクについて解説します。
有効なメールアドレスだと相手にバレることがある
詐欺メールのなかには、開封したかどうか確認できる機能がついたものがあります。そのため、開封してしまうとアドレスが有効であることを送信者に知られてしまうリスクがあります。
この機能は「Webビーコン」と呼ばれる、メール内に埋め込まれた小さな画像ファイルを用いた技術によるものです。受信側のメールが自動で画像データをダウンロードする設定になっている場合、Webビーコンが自動的にダウンロードされます。これにより、送信側にメールの開封状況が伝わってしまいます。
有効なアドレスだとわかれば、さらに多くの詐欺メールが送られてくる可能性が高まります。また、アドレスをほかの詐欺グループに売られるリスクもあるでしょう。こうした被害に遭わないよう、不審なメールは開封せず、すぐに削除することが大切です。
開いただけでウイルスに感染する可能性がある
詐欺メールを開封しただけでもウイルスに感染する危険性があります。特に注意が必要なのは、HTML形式のメールです。
HTML形式のメールとは、Webページのように画像や装飾を含むメールのことです。通常は見た目をよくする目的で使用されますが、犯罪の手段として悪用されるケースもあります。具体的な手口としては、悪意のあるスクリプトをメールに埋め込み、受信者がメールを開いた瞬間にスクリプトを実行させて、ウイルスをダウンロードさせることが挙げられます。
このようなウイルスは、パソコンやスマホの動作を妨害したり、個人情報を盗み取ったりするおそれがあります。ウイルスに感染してからでは対処が難しくなるため、送信元が不明なメールや、見知らぬメールは開かないよう注意しましょう。また、メールソフトの設定から、HTML形式のメールを自動的にテキスト形式で表示するように設定することも有効な対策です。
詐欺メールの現状
ここでは、詐欺メールによる被害の現状と、代表的な手口について詳しく解説します。
詐欺メールによる被害は増えている
詐欺メールの手口は年々巧妙化し、有名企業や公的機関になりすましたものが増加しています。これに伴い、被害も拡大傾向にあるのが現状です。
2023年上半期にかけて、サイバー犯罪の状況は深刻さを増しています。特に注目すべきは、フィッシング被害に起因するクレジットカードの不正利用やインターネットバンキングの不正送金が急増していることです。フィッシング対策協議会のデータによると、フィッシング情報の届け出件数は、2023年下半期で過去最多を更新しています。ECサイト大手やクレジットカード会社だけでなく、ポイント事業などの公共サービス、交通系サービスになりすました詐欺が報告されています。
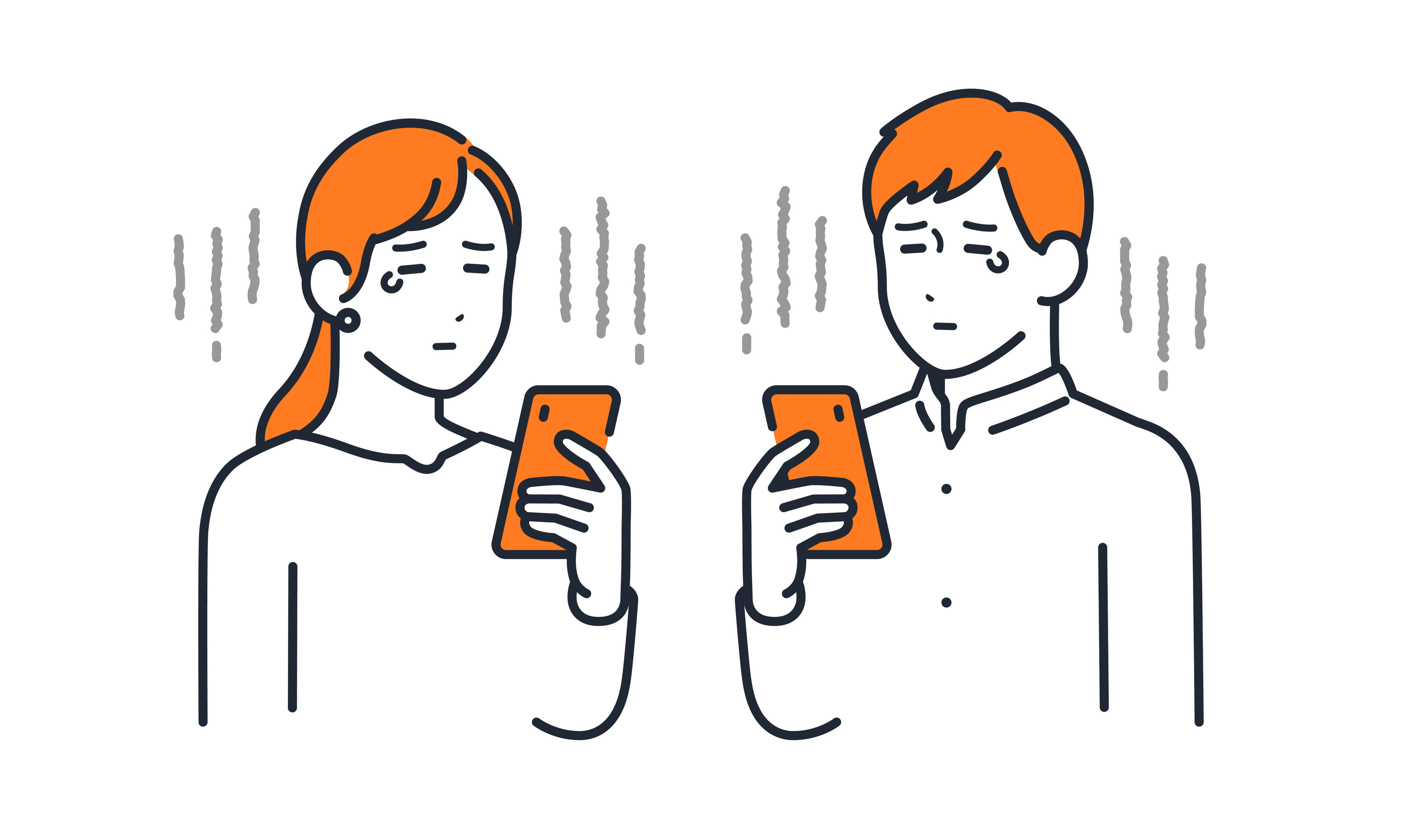
出典: フィッシング対策協議会「フィッシングレポート 2024」
詐欺メールの代表的な手口
詐欺メールの主な手口としてまず挙げられるのは、IDやパスワードの変更を促すメールです。詐欺メールを開くと、「セキュリティ上の問題が発生したため、アカウント情報の更新が必要」のような文面で偽のログインページに誘導され、ログイン情報の入力を求められます。ここで情報を入力するとアカウント情報が流出してしまうおそれがあります。
また、宅配便の不達通知を装ったメールも典型的な手口の一つとして挙げられます。「配達できなかったため、再配達の手続きが必要」などと告げ、個人情報の入力を求めてきます。特に、オンラインショッピングを頻繁に利用する人が標的になりやすいでしょう。
加えてクレジットカード会社を装った詐欺もよく見られる手口の一つです。「カードの有効期限が切れたため、更新が必要」といった内容で煽り、カード情報の入力を促します。これらの手口に引っかかってしまうと、個人情報の流出による金銭的な被害のリスクも高まってしまいます。
詐欺メールの主な種類
詐欺メールにはさまざまな種類があります。ここでは、代表的な詐欺メールの種類として「スパムメール」「フィッシングメール」「架空請求メール」について詳しく解説します。
スパムメール
スパムメールとは、不特定多数の人に対して一斉に送信される迷惑メールのことです。広告目的のものもあれば、詐欺やウイルス感染を狙った悪質なものもあります。
例えば、ウイルスが仕込まれた添付ファイルを開かせようとするものや、受信者を偽のウェブサイトへ誘導し、個人情報を盗み取るものなどがあるため注意が必要です。
スパムメールについての詳細や対策方法は以下の記事で紹介をしておりますので、気になる方はぜひご覧ください。
スパムメールとは?危険な理由や被害を防ぐ対策を解説
フィッシングメール
フィッシングメールは、金融機関や大手サービスを装い、受信者の個人情報を騙し取ることを目的とした詐欺メールの一種です。一般的には「あなたのアカウントに問題が発生しました」「支払い情報を更新してください」といった内容で、不安を煽るような文面になっていることが特徴です。
メール内のリンクをクリックすると、精巧に作られた偽サイトに誘導され、ログインIDやパスワード、クレジットカード情報などを入力させようとします。万が一、入力してしまうと、個人情報の悪用やクレジットカードの不正利用に遭う可能性があります。
架空請求メール
架空請求メールとは、実際には存在しない料金の支払いを求める詐欺メールです。「有料サイトの未納料金が発生しています」「法的措置を取る前に支払いをしてください」など、受信者の不安や恐怖を煽る文面を用いるのが特徴です。
架空請求メールのなかには、実在する企業やサービスを装い、未払いの料金があるかのように装うものもあります。指定された口座への振り込みや個人情報の入力を促されても、応じないようにしましょう。
【ケース別】詐欺メールを開いてしまった場合の対処法
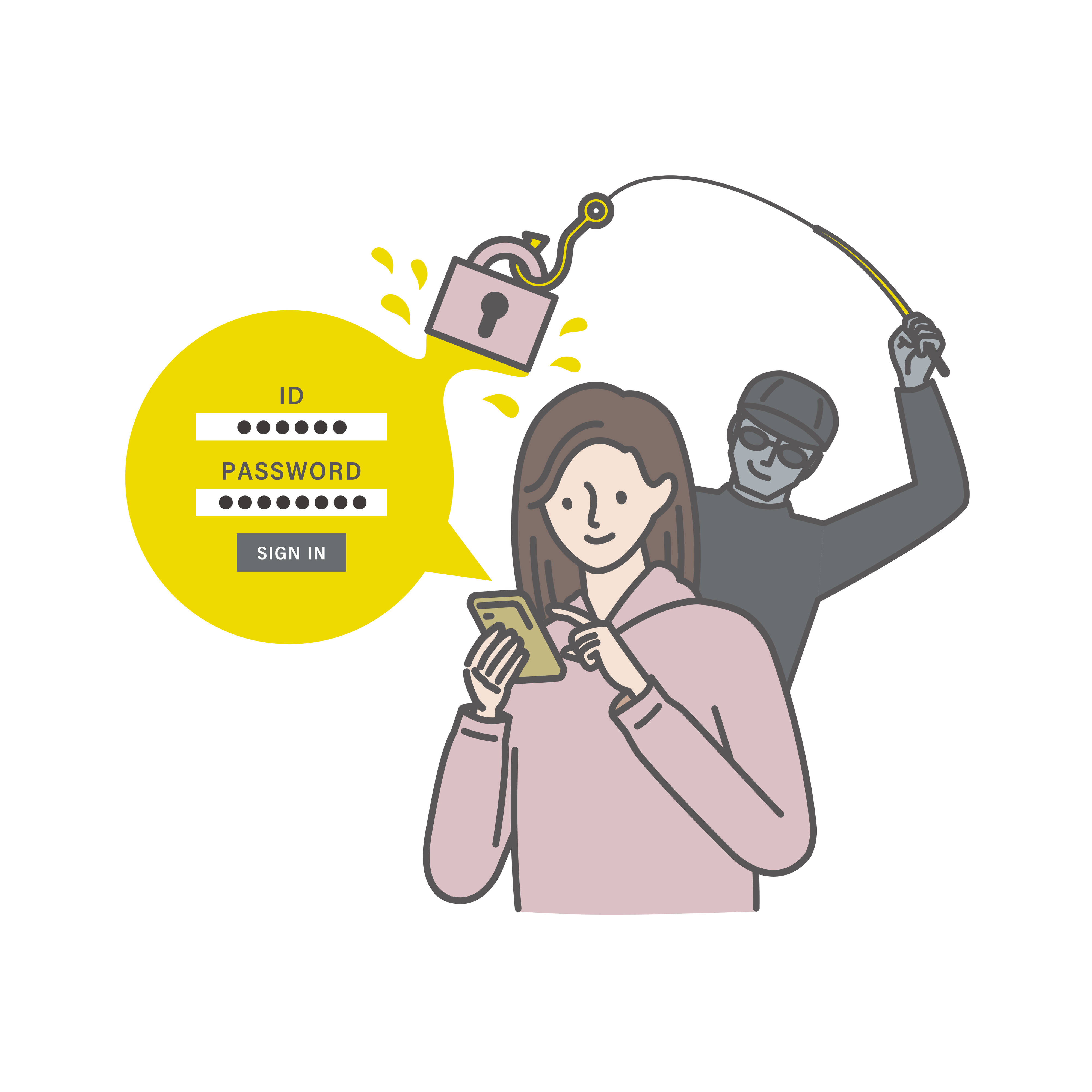
詐欺メールを開いてしまった場合の被害を最小限にするため、状況に応じた適切な対処法を知っておくことが大切です。ここでは、ケース別に具体的な対処法を解説します。
メールを開いただけの場合
スパムメールを誤って開いてしまった段階では、深刻な被害に遭うリスクは低いでしょう。しかし、なかには開封するだけでウイルス感染の可能性があるメールも存在するため、念のために対策を講じることをおすすめします。
まず、端末のネットワーク接続を切断しましょう。これにより、万が一ウイルスに感染していた場合でも、外部への情報漏洩を防止できる可能性が高まります。次に、セキュリティ対策サービスなどを活用して端末をスキャンしましょう。セキュリティ対策サービスとは、ウイルスや不正なプログラムから端末を守るためのソフトやアプリのことです。
会社支給の端末を使用している場合は、IT部門や上司に状況を報告することも大切です。組織全体のセキュリティを守るためにも、迅速な対応が求められるでしょう。
URLへのアクセスや添付ファイルを開いた場合
スパムメールに含まれるURLにアクセスしたり、添付ファイルを展開したりした場合は、ウイルス感染や個人情報の流出リスクが高まるため、より慎重な対応が必要となります。
まずは、メールを開いただけの場合と同様に端末のネットワーク接続を切断しましょう。次に、セキュリティソフト・アプリを使用してスキャンを行います。さらに、ブラウザの履歴やCookieの削除も行っておくとあんしんです。Cookieとは、Webサイトがユーザーの情報を一時的に保存するデータのことで、Cookieを削除することで不正アクセスのリスクを軽減できます。
アカウント情報を入力した場合
アカウント情報を入力してしまった場合は、迅速な対応が求められます。まず、該当するサービスのIDとパスワードを直ちに変更しましょう。これにより、不正アクセスのリスクを軽減できます。
銀行口座やクレジットカードの情報を誤って入力してしまった際は、すぐに金融機関やクレジットカード会社に連絡しましょう。不正利用の危険性があるため、カードの停止や口座の監視強化を依頼することが重要です。
基本的に、同じパスワードを複数のサービスで使い回すことは避けたほうがよいでしょう。使い回していたことが発覚した場合は、すべてのアカウントの情報が流出してしまい、深刻な被害を招く可能性があります。複数のパスワードを管理することは大変に感じるかもしれませんが、情報流出の連鎖を防ぐ上では非常に大切です。
会社の端末や業務用アカウントで情報を入力してしまった場合は、速やかに上司やIT部門に報告しましょう。
アプリをインストールした場合
不審なアプリをインストールしてしまうと、端末全体に影響をおよぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。まずは、該当のアプリを直ちに削除しましょう。
次にセキュリティソフトやアプリを持っている場合はそれらを使用し、端末全体のスキャンを行います。ウイルス削除の機能がついているソフトやアプリであれば、ウイルス自体の削除も可能です。
併せて、端末内のすべてのアプリやサービスのパスワードを変更することもおすすめします。通常のパスワードに加えて、別の認証方法(例:スマホへの確認コード送信)を組み合わせる「二段階認証」を行い、セキュリティを強化しましょう。
詐欺メールを見分ける方法

詐欺メールを見抜く方法はいくつかあります。一例として、「一斉送信されていないか」を確認することが挙げられます。特に、身に覚えのない他人のメールアドレスがCCに含まれている場合は、詐欺メールなどの怪しいメールである可能性が高いといえるでしょう。
受信したメールが本物なのか判断に迷う場合は、公式サービスに直接問い合わせるのが大切です。ただし、メール内に記載された連絡先は偽装されている可能性があるため、必ず公式のWebサイトなどで確認した連絡先を使用してください。
また、送られてきたメールの内容については、以下の点にも注意を払いましょう。
● 「送信元」は信頼できるか
● 「件名」は行動を急かすような内容でないか
● 「本文」の内容や表現に違和感はないか
詳しくは以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
詐欺メールのリスクを低減させる対策
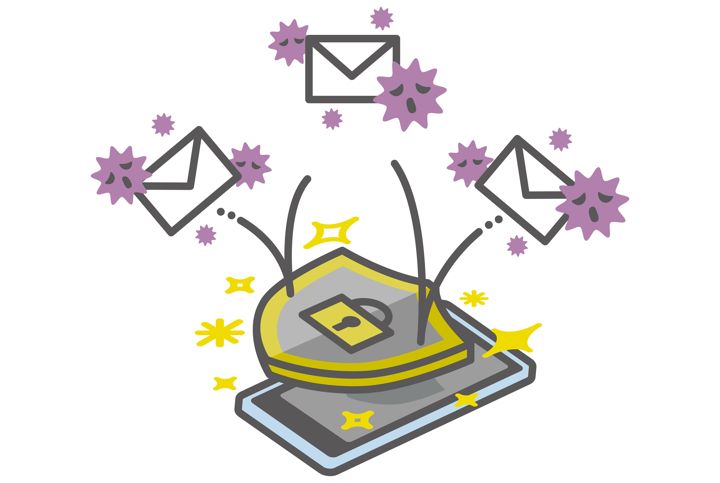
詐欺メールが届かないようにするためには、さまざまな対策を講じることが重要です。ここでは、具体的な対策方法を5つ紹介します。
メールの拒否設定を利用する
多くのメールサービスには、迷惑メール対策の機能が備わっています。これらを活用することで、不要なメールを効果的に排除できるでしょう。メールサービスでは、特定のドメインや、アドレスからのメールを自動的に拒否する設定が可能です。
頻繁に迷惑メールが届く特定のドメインをブロックリストに追加することで、そのドメインからのメールを受信しないようにできます。また、信頼できる送信者のアドレスをホワイトリストに登録することも有効です。これらの設定を適切に行うことで、迷惑メールの受信リスクを大幅に低減できます。
プロバイダ側のメール受信制限を活用する
多くのインターネットサービスプロバイダ(ISP)では、メールの受信制限機能を提供しています。たとえばドコモの場合、「特定URL付メール拒否設定」「詐欺/ウイルスメール拒否設定」「大量送信者からのメール拒否設定」などが利用可能です。これらの機能を活用することで、潜在的に危険なメールを事前にブロックできます。
メールフィルタリングを活用する
上記の対策を講じても詐欺メールが届く場合、メールフィルタリングを活用しましょう。メールフィルタリングとは、スパムメールを自動で判定してブロックしてくれたり、警告表示をしてくれたりする機能のことです。
ドコモが提供する「あんしんセキュリティ」では、迷惑メールを自動的に専用フォルダに振りわける機能があります。さらに、電話帳に登録されたアドレスからのメールのみを受信する設定も可能です。これらのサービスを利用することで、より高度な迷惑メール対策が実現できるでしょう。
複雑なメールアドレスにする
迷惑メールの送信者は、ランダムにアドレスを生成して大量のメールを送信することがあります。そのため、単純なアドレスほど生成されやすく、結果として詐欺メールを送られやすくなるでしょう。
メールアドレスを作成する際は、できるだけ複雑なものにすることをおすすめします。具体的には、英字の大文字と小文字・数字・記号を組み合わせたアドレスが効果的です。たとえば、「tanaka123@example.com」よりも、「Tanaka_123_AB@example.com」のようなアドレスの方が、ランダム生成されにくいでしょう。
会員登録は信頼できるサービスのみにする
オンラインサービスの利用が日常的になった昨今、会員登録を行う機会も増えています。しかし、安易に登録を行うことは、個人情報漏洩のリスクを高めるため注意が必要です。会員登録を行う前にサービスの評判などを調べて、信頼性を十分に確認しましょう。
不審なサービスへの登録を避けることで、個人情報の保護だけでなく、詐欺や不正アクセスのリスクも軽減できます。
まとめ
スマホで詐欺メールが疑われる不審なメールを開いてしまった場合は、冷静な対応が大切です。メールを開いただけでは大きな問題は生じませんが、URLにアクセスしたり添付ファイルを開いたりすると、ウイルス感染のリスクがあるため注意が必要です。アカウント情報を入力してしまった際は、すぐにパスワードの変更を行いましょう。
詐欺メールを見分けるポイントは、送信元アドレスの確認、日本語表現のチェック、一斉送信の有無の確認などがあります。予防策としては、信頼できるサービスのみに会員登録すること、複雑なメールアドレスを使用すること、メールソフトにフィルタを設定することなどが有効です。さらに、プロバイダのメール受信制限機能やセキュリティソフト・アプリの活用も検討し、スマホの安全性を高めましょう。