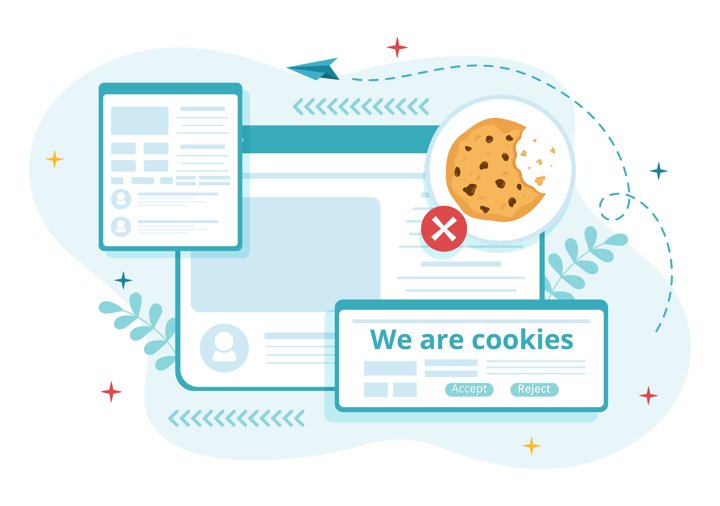インターネットトラブルの主な事例と具体的な対策を紹介

現代社会において、インターネットは生活に欠かせない存在です。一方で、インターネット上には誹謗中傷や個人情報の流出、オンライン詐欺などのさまざまなリスクが潜んでいます。
本記事では、子どもと大人の双方に影響をおよぼすインターネットトラブルの主な事例を紹介するとともに、安全にインターネットを利用するための具体的な対策について詳しく解説します。
目次
インターネットトラブルの主な事例

近年、子どものスマホ所持率増加に伴い、インターネットトラブルも深刻化しています。こども家庭庁が実施した「令和5年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」によれば、自分専用のスマホを使っている青少年の割合は次のとおりです。
- 小学生(10歳以上):70.4%
- 中学生:93.0%
- 高校生:99.3%
スマホは子どもとの連絡がスムーズになる一方で、さまざまなトラブルに発展するリスクがあります。
注意しなければならないのは、子どもだけではありません。2024年版『消費者白書』では、SNS関連の相談で最も多かった年代は50代であるとわかっています。このように、インターネットトラブルは子どもだけでなく大人も注意が必要です。
子どもが関係するインターネットトラブルの事例
子どもは大人に比べて危険を察知する能力が未熟なため、インターネットのリスクを十分に理解しないままトラブルに巻き込まれることが少なくありません。
ここでは子どもが巻き込まれやすい、巻き込まれるおそれがある主な事例を紹介します。
誹謗中傷やいじめ
インターネット上での誹謗中傷やいじめは深刻な社会問題です。SNSでの悪口やデマの拡散、グループチャット内での仲間外れなどで、子どもが不登校になったり精神的に追い詰められたりするケースは少なくありません。
また、誹謗中傷の被害に遭った場合はサイト管理者や公的機関を通じて削除依頼することができます。しかし、仮にその投稿が拡散されると「デジタルタトゥー」※としてインターネット上に残り、完全に消去することが困難になる可能性もあります。
一つの軽率な投稿が、長期間にわたって被害者を苦しめる可能性があるということを理解することが必要です。
※「デジタルタトゥー」とは、インターネット上で拡散された情報が半永久的に残ることを意味する言葉
個人情報の流出
SNSなどでは、子どもが無意識のうちに自宅の住所や学校名を投稿し、それが悪意ある第三者に悪用されることがあります。また、投稿した写真から撮影場所を特定され、ストーカー被害や詐欺に巻き込まれるリスクも否めません。
さらに、名前やメールアドレスが勝手に使われ、不正アクセスやなりすましの被害につながる可能性もあります。
SNSやオンラインゲームで知り合った人からの誘い出し
SNSやオンラインゲームを通じて知り合った相手に、犯罪を目的として誘い出されるケースが増加しています。警察庁がまとめた「インターネット利用における 子供の性被害等の防止について」によると、SNSに起因する重要犯罪等の被害児童数は2014年には38件でしたが、2023年には225件にまで増えました。この数字には、殺人や強盗、不同意わいせつ、不同意性交等などが含まれています。
また、出会い系サイトに限らず、一般的なSNSやゲームのチャット機能を悪用した犯罪も後を絶ちません。見知らぬ人と簡単にやりとりできる環境が整っているため、子どもが警戒心を抱かないまま会話を続け、結果として被害に遭うケースが増えているのが現状です。
意図しない有料サービスの利用
「無料」と表示されたオンラインゲームで、子どもが意図せず高額な有料アイテムを購入し、請求トラブルに発展するケースも増えています。有料アイテムの購入時に課金の仕組みがわかりにくく、気づかないうちに高額な請求が発生することも少なくありません。
国民生活センターによると、オンラインゲームに関する相談件数は2021年には7,126件だったものが、2023年には8,432件に増加しています。
闇バイト
SNSを通じて「高額バイト」や「即日即金」などの甘い言葉を使い、犯罪に勧誘する「闇バイト」も大きな問題です。近年、強盗や特殊詐欺などの重大犯罪に未成年が関与するケースが相次いでいますが、背景にはSNSを悪用した違法な求人があると考えられています。
「簡単に稼げる」と誤解し、知らぬ間に犯罪に手を染めてしまう子どもも少なくありません。闇バイトは逮捕される可能性があるだけでなく、一度関与すると犯罪組織から抜け出せなくなるおそれもあります。
大人も注意が必要なインターネットトラブルの事例
インターネットトラブルは、子どもだけでなく大人も巻き込まれるおそれがあります。特に、迷惑メールやフィッシング詐欺、誹謗中傷といったトラブルには注意が必要です。
ここでは、大人が特に注意すべき事例を紹介します。
迷惑メール
迷惑メールは広告目的のメールから架空請求、フィッシング詐欺などの詐欺メールまで、種類はさまざまです。
「重要なお知らせ」「あなたの口座が危険にさらされています」など思わず閲覧したくなってしまう件名で送られてくることが多く、本文に記載のリンクから危険なサイトにアクセスさせたり、添付ファイルからウイルスに感染させたりしようとします。
迷惑メールについて詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【事例紹介】迷惑メールのよくある手口を解説!届く理由や対処法は?
誹謗中傷
インターネット上での誹謗中傷も深刻なトラブルの一つです。誹謗中傷とは、特定の個人や企業に対し、相手の人格を否定したり、根拠のない嘘を広めたりする行為です。名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪に該当する可能性もあり、法的責任を問われることもあります。
インターネット上の違法・有害情報に対する相談を受けつけている総務省の委託事業「違法・有害情報相談センター」の報告によると、2015年度から2023年度までの相談件数は毎年5,000件を超えており、2023年度には過去最多の6,463件に達しました。そのうち58.5%が「相談者の名誉や会社の信用を貶めるような情報(誹謗中傷など)」となっており、過半数を占めていることがわかっています。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺とは、銀行やクレジットカード会社を装った偽のメールやWebサイトを使用し、個人情報を盗み取る詐欺のことです。偽サイトにログイン情報を入力させたり、偽アプリをインストールさせて情報を抜き取る方法などが用いられます。
最近では、SMSを利用したフィッシング詐欺も急増しており、「あなたの口座に不正アクセスがありました」「本人確認が必要です」といった内容で、偽サイトへ誘導する手口が多いです。
SMSのフィッシング詐欺について、詳しくは次の記事を参考にしてください。
サポート詐欺
サポート詐欺は、インターネット利用中に「あなたのパソコンがウイルスに感染しました」「至急サポートセンターに連絡してください」などの偽警告を表示し、利用者を騙してサポート契約や高額な料金を請求する詐欺です。特に、突然ポップアップで警告が表示され、記載の電話番号への連絡を促されるケースは要注意です。
番号に電話をかけると、偽のカスタマーサポート担当者が対応し、「問題を解決するには有償のサポートが必要です」と説明します。プリペイドカードや電子マネーを使って支払いを求めるケースもあり、一度支払うと取り戻すのが困難です。
インターネットトラブルを防ぐための対策

安全にインターネットを利用するためには、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、検索エンジンのセーフサーチ設定、フィルタリングサービスやセキュリティ対策サービスの活用といった、具体的な対策方法について紹介します。
セーフサーチを設定する
セーフサーチとは、Googleなどの検索エンジンに搭載されている、検索結果上の露骨な表現を含むコンテンツを除外する機能のことです。使用すると、性的なサイト・暴力的なサイトなどの有害・不適切なサイトが検索結果から自動的に除外されます。
ただし、セーフサーチだけではすべてのリスクを排除できません。ほかのセキュリティ対策と併用することが重要です。
なお、設定方法については次の記事を参考にしてください。
セーフサーチとは?設定が必要な理由やAndroid・iPhone別に設定方法を紹介
フィルタリングサービスを活用する
フィルタリングサービスを活用すると、不適切なサイト(性的なサイト・暴力的なサイト・出会い系サイトなど)へのアクセスを制限できます。
たとえば、ドコモの「フィルタリングサービス」では、学齢別(小学生・中学生・高校生・高校生プラス)にルールを設定することで、適切な制限レベルを自動で適用することが可能です。そのため、年齢に応じたインターネットの利用環境を整えることができます。
セキュリティ対策サービスを活用する
セーフサーチやフィルタリングでブロックできるのは、主に性的・暴力的・出会い系などの有害・不適切なサイトです。ウイルスサイトやフィッシング詐欺サイトといった脅威に対しては、別の対策が求められます。
特に、迷惑メールやフィッシング詐欺は、セーフサーチやフィルタリングサービスだけでは防ぐことが難しいため、セキュリティ対策サービスの利用が推奨されます。
たとえば、「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「危険サイト対策」機能は、閲覧しようとしているサイトがウイルスサイトやフィッシング詐欺サイトなどの危険なサイトだった場合、警告を表示してくれます。また、「迷惑メール対策」機能は、迷惑メールを自動で専用のフォルダに振り分けてくれる上に、既存の迷惑メール対策と併用可能です。
まとめ
インターネットの普及に伴い、誹謗中傷や個人情報の流出、オンライン詐欺などのトラブルが増加しています。特に、子どもは危険を察知しにくく、SNSやオンラインゲームを通じた犯罪被害や、高額な課金トラブルに巻き込まれるケースが目立ちます。
また、大人も迷惑メールやフィッシング詐欺、誹謗中傷の被害に遭うリスクがあるため、対策が欠かせません。安全にインターネットを利用するには、フィルタリングやセキュリティ対策サービスを活用し、リスクに対して適切な備えを実施することが重要です。