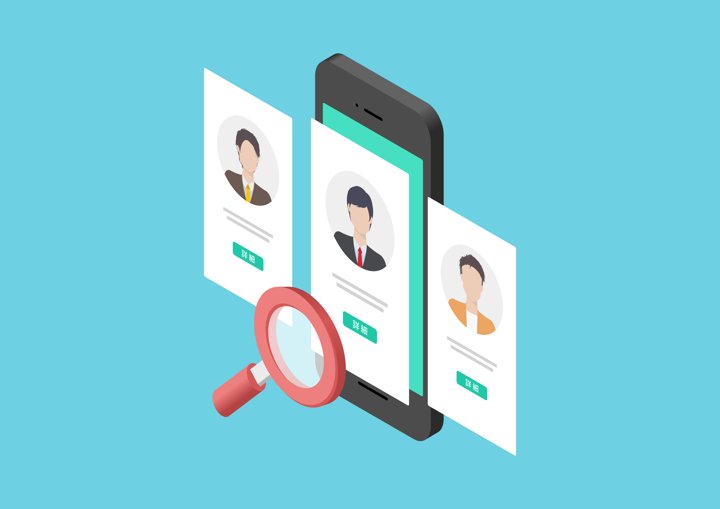生成AIのセキュリティリスクとは?具体的な対策を紹介

近年、生成AIの活用が急速に広がり、文章や画像、音声の生成が容易になりました。一方で、情報漏洩やなりすまし、フェイクニュースなどのセキュリティリスクも懸念されています。
特に、悪意ある第三者によるAIの悪用は、企業や個人、さらには社会全体に深刻な影響をおよぼしかねません。本記事では、生成AIがもたらすセキュリティリスクの具体例を解説し、リスクから身を守るための対策について詳しく紹介します。
目次
生成AIによるセキュリティリスクとは?

生成AIは便利な技術ですが、発展に伴いセキュリティリスクも増大しています。たとえば、不正なアクセスや操作によって機密データが漏洩するリスクがあり、企業や個人の重要な情報が悪用される可能性があります。
また、生成AIを悪用し、詐欺やなりすまし、フェイクニュースの捏造を行う事例も増えています。特に高度なAIによるフェイクニュースの拡散は、社会に深刻な影響をおよぼすおそれがあります。これらのリスクを回避し、生成AIを安全に活用するためには、適切なセキュリティ対策の導入が不可欠です。AI技術の進化とともに、これらのリスクを抑える取組みが求められています。
セキュリティリスクなど生成AIに関する主なリスク
生成AIの発展により、多くの分野で業務の効率化が進んでいます。一方でセキュリティリスクをはじめとしたいくつかのリスクが存在することも指摘されており、その利便性とリスクを理解した上で活用することが必要です。
ここでは、生成AIに関する代表的なリスクについて解説します。
個人情報の漏洩
生成AIを利用する際、誤った使い方によって個人情報が漏洩するリスクが伴います。たとえば、AIが学習したデータをもとに第三者へ回答する際、過去の学習データに個人情報や機密情報が含まれていると、意図せず公開されてしまう可能性があるでしょう。
また、企業がAIに顧客情報を入力し、不適切に共有されることで情報漏洩につながるケースも考えられます。さらに、クラウド上で動作するAIサービスでは、データの保存や通信時のセキュリティ対策が不十分な場合、外部からの不正アクセスを受ける危険も否めません。
事実と異なる内容の生成(ハルシネーション)
生成AIは、人間が書いたような自然な文章やリアルな画像を生成できます。しかし、その精度には限界があり、事実と異なる情報を作り出す「ハルシネーション」と呼ばれる現象が発生することがあります。
たとえば、歴史的事実とは異なる説明を生成したり、実在しない人物や出来事について誤った情報を出力したりすることがあります。また、意図せず著作権を侵害する表現や、差別・偏見を助長する内容が含まれる場合も想定されるでしょう。
こうした誤情報が拡散すると、社会的な混乱や法的問題につながるおそれがあります。そのため、生成AIが提供する情報は常に正しいとは限らないことを認識し、情報源を確認することや、ほかの信頼できる資料と照らし合わせることが不可欠です。
生成される情報の汚染(データポイズニング)
データポイズニングとは、悪意ある第三者が意図的に誤った情報や偏ったデータをAIの学習データに混入させ、AIの判断を歪める攻撃手法です。たとえば、特定の企業や製品に対する否定的な情報を組み込むことで、AIが不正確な評価を出すように誘導するケースが考えられます。
また、政治的な偏向を強めるデータをAIに学習させることで、特定の思想や立場に偏った出力が行われる危険性もあります。このようなデータ汚染は生成AIの信頼性を低下させ、誤った情報を広める原因となるため、注意しなければなりません。
対策としては、学習データの品質管理を徹底し、外部からの不正なデータ改ざんを防ぐ仕組みを導入することが重要です。さらに、定期的な再学習を実施し、AIの精度を維持する取組みも求められます。
ディープフェイク
ディープフェイクとは、「ディープラーニング」と「フェイク」を組み合わせた造語であり、AI技術を活用して人工的に人物の動画や音声を合成する技術です。この技術を使うことで、実在する人物の映像を操作し、あたかも本人が動き、話しているかのような動画を作成できます。
近年では、ディープフェイクを悪用したなりすまし詐欺やフェイクニュースの拡散が社会問題となっています。たとえば、企業の役員や政治家、有名人などの顔や声のデータを元に偽造し、信用を失墜させるような虚偽の発言を作り出すケースです。
また、本人認証の突破に悪用され、不正なアカウント作成や金融詐欺の被害に遭うリスクも懸念されています。このような被害を防ぐためには、ディープフェイク検出技術の導入や、映像・音声の真正性を確認する対策が必要です。
悪意のあるプログラムの作成
生成AIは、通常の利用では有益なツールですが、悪意のある目的に使用される危険性もあります。特に、AIを使って巧妙なフィッシングメールを作成したり、マルウェア(スマホやユーザーに被害をもたらすことを目的とした、悪意のあるソフトウェア)を開発したりするケースが懸念されています。
たとえば、自然な文章を自動生成できるAIを悪用し、詐欺メールを作成することで、多くの人を騙す手口が増加しています。また、ウイルス感染を目的としたプログラムを自動生成するAI技術も登場しており、サイバー攻撃のリスクが高まっています。
こうした脅威に対処するためには、セキュリティアプリやソフトを常に最新の状態に保つことや、身に覚えのないメールのリンクにアクセスしないといった基本的な対策を徹底することが重要です。さらに、企業や組織においては、従業員へのセキュリティ教育を強化し、被害を未然に防ぐ取組みが求められます。
生成AIを利用する際のセキュリティ対策

生成AIを活用する際には利便性の恩恵を受けるだけでなく、同時にセキュリティリスクへの対策も欠かせません。特に個人情報の漏洩や誤情報の拡散、AIの悪用といった問題が懸念されるため、適切な対応が必要です。
基本的な対策として、個人情報を含むデータをAIに入力しないことや、人の手によるチェックを徹底することが挙げられます。また、セキュリティ対策サービスを活用することで、情報漏洩のリスクを軽減することも可能です。
ここでは、生成AIを安全に利用するための具体的な対策について解説します。
個人情報に関することを入力しない
生成AIを利用する際は、個人情報や機密情報の取扱いに十分注意する必要があります。AIの学習データに入力された情報が、ほかのユーザーへの回答として出力される可能性があるため、不用意な情報入力は避けるべきです。
特に名前や住所、クレジットカード情報などの個人情報は、不用意に学習させないようにするのが賢明でしょう。
人によるチェックを通す
生成AIが出力したコンテンツは、正確であるとは限りません。そのため、公開前に人によるチェックを行うことが重要です。
たとえば誤った情報を出力していないか、機密情報や個人情報を含めていないか、著作権の侵害や不適切な表現がないかなど、生成AIのコンテンツを過信することなく慎重に確認する必要があります。
セキュリティ対策サービスを活用する
生成AIを安全に利用するためには、セキュリティ対策サービスを活用するのも効果的な方法の一つです。たとえば、ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」には、「ダークウェブモニタリング」機能が搭載されています。
この機能を利用すると、ダークウェブ上に個人情報が流出していないかを監視し、情報が流出した際に通知を受け取ることが可能です。たとえば、仮に生成AIがきっかけで個人情報が漏洩し、ダークウェブ上にも流出した場合に通知を受け取ることができ、ID・パスワードの変更やクレジットカードの利用を停止するなど、被害を最小限に防ぐ対応を取ることができます。こうしたセキュリティ対策を活用することで、生成AIをよりあんしんして利用できる環境を整えることができます。
まとめ
生成AIの活用が進む一方で、個人情報の漏洩や誤情報の生成、データポイズニング、ディープフェイクなど、さまざまなリスクが存在します。これらのリスクを最小限に抑えるためには、個人情報をAIに入力しない、AIが生成した情報を人がチェックする、そしてセキュリティ対策サービスを活用することが重要です。
特に、企業での利用においては、適切なガイドラインの策定や多層的なチェック体制を整えることで、安全性を確保できます。AI技術は今後も進化を続けるため、利用者自身がリスクを理解し、適切な対策を講じながら活用することが求められます。生成AIをあんしんして活用するために、最新のセキュリティ情報を把握し、適切なリスク管理を行いましょう。