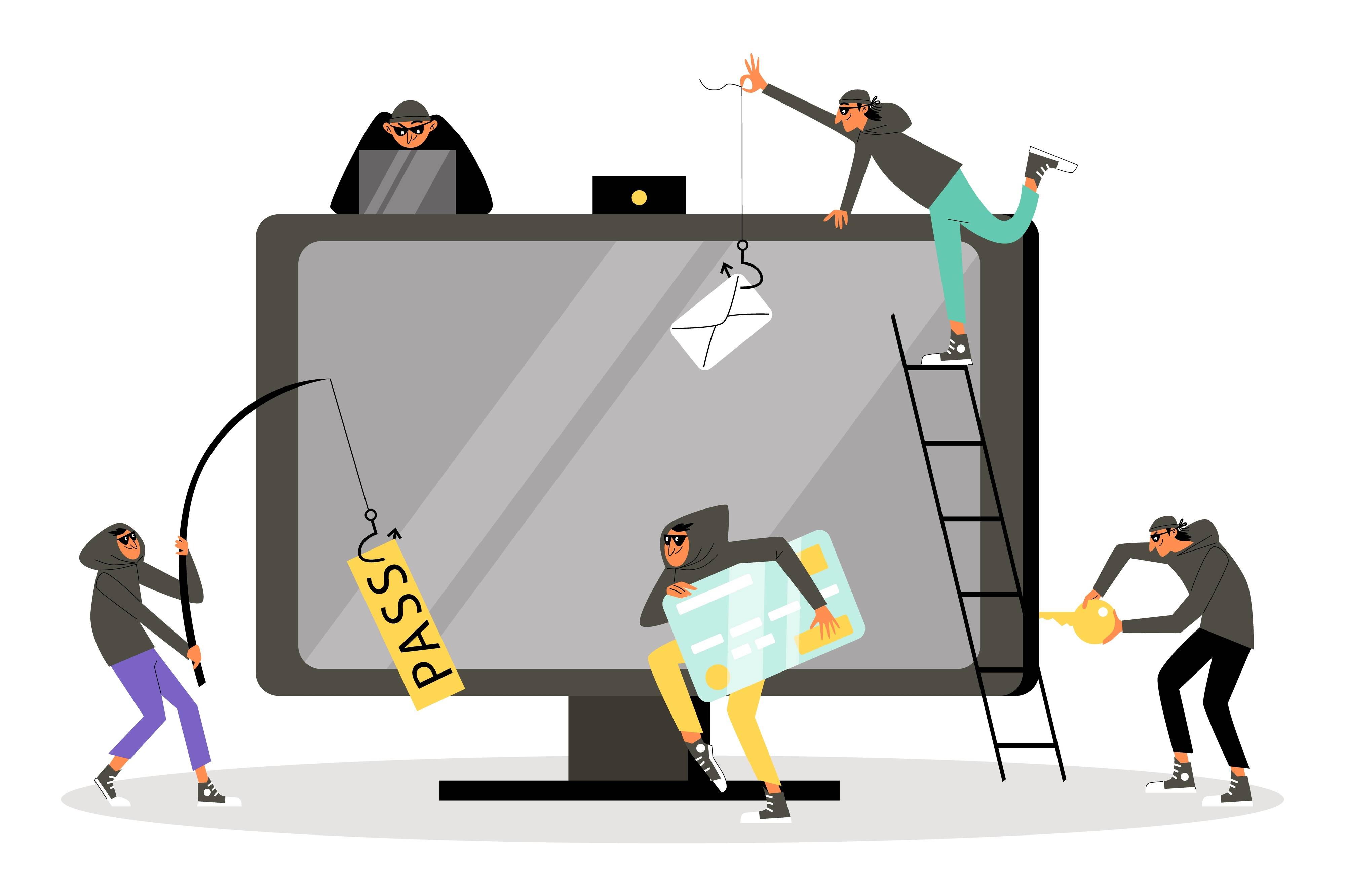フェイクニュースへの対策は?ネットに潜む脅威から自分を守ろう

近年、フェイクニュースと呼ばれる事実ではない情報が公開されていることは少なくありません。フェイクニュースが広まると、多くの人がその内容に感化されて世論や国際情勢などに影響を与えるケースもあるため、嘘の情報に騙されないための適切な対策が求められます。
本記事では、フェイクニュースの概要と対策が必要とされる理由、フェイクニュースによって引き起こされるリスクを解説します。具体的なフェイクニュース対策も紹介しますので、お役立てください。
目次
フェイクニュースとは

フェイクニュースとは、メディアやブログ、SNSなどで公開される、事実ではない情報のことです。フェイクニュースが多くの人に広まると、世論や政治などに影響を与えることもあります。実際に海外では選挙や感染症などをはじめ、さまざまなフェイクニュースが広まり、日本でも拡散されています。
フェイクニュース対策が必要な理由
近年、生成AIの普及により、本物そっくりな「フェイク」が急増しています。総務省の調査によれば、『偽・誤情報を「週1回以上」(毎日、またはほぼ毎日+最低週1回)見かけた割合』は次のとおりでした。
- 検索サービス:36.0%
- ソーシャルネットワーキングサービス(SNS):48.0%
- 新聞社やテレビ局のニュースサイト:29.3%
- ニュース系アプリ・サイト:33.6%
- まとめサイト:31.5%
- 動画投稿・共有サービス:38.7%
参考:総務省|令和5年度国内外における偽・誤情報に関する意識調査結果紹介
このように、さまざまな媒体を通して、実に3人に1人がフェイクニュースを週に1回以上目にしているとわかっています。
さらにフェイクニュースはSNSやWebメディアを通じて瞬時に拡散します。特に、感情を煽るようなニュースは人々の関心を集めやすく、誤情報が事実よりも拡散しやすい傾向があります。
そのため、たとえ好奇心や感情を揺さぶられるニュースに触れたとしても、真に受けずに冷静な判断を行う知識と経験が必要です。常日頃から目にするインターネット上の「ニュース」「記事」という媒体が発信する情報に対して疑いの目を持つことは、インターネットに潜む脅威から身を守ることにつながります。
ただし、前述のとおりインターネットには多様な脅威が潜んでおり、その手口はますます巧妙化しています。そのため、インターネットリテラシーの向上とともにセキュリティ対策も必要です。
フェイクニュースによって引き起こされるリスク
フェイクニュースに影響されると、誤った行動を取ってしまったり、拡散によって罪に問われたりするリスクが生じます。ここでは、フェイクニュースによって引き起こされるリスクについて詳しく解説します。
誤った行動を取ってしまう
フェイクニュースによって誤った行動を取ってしまう具体例に、2020年2月末頃に「新型コロナウイルスの影響でトイレットペーパーが不足する」というフェイクニュースが生じ、店舗のトイレットペーパーが品薄になる事態が生じたケースが挙げられます。
また、災害時のフェイクニュースを信じて安全な場所に避難できなかったり、誤った情報に基づいて行動したりして、危険な目に遭う可能性もあります。
拡散することで罪に問われる可能性もある
フェイクニュースを拡散すること、つまり偽情報・誤情報を投稿または拡散することは、偽計業務妨害や詐欺などの罪に問われる可能性があります。場合によっては、損害賠償責任を負う可能性もあるため、注意が必要です。
たとえば、熊本地震の際に、動物園からライオンが逃走したという虚偽情報がSNSで拡散されて動物園や警察に問合せが殺到し、投稿者は偽計業務妨害容疑で逮捕される事件がありました。
また、あおり運転事故に関して、実際には無関係な会社に被告が勤務していたとするデマが拡散され、無関係な会社が根拠のない非難や無言電話を受けて休業に追い込まれたために、投稿者らに損害賠償が命じられたケースもあります。
フェイクニュースに騙されないための対策
前述のように、フェイクニュースに影響されると自身への危険が生じるおそれがあります。フェイクニュースに騙されないために、以下の対策を行いましょう。
情報源を確認する
フェイクニュースに騙されないためには、情報源の確認が大切です。公的機関、学術機関、専門家の論文などであるか、信頼できる報道機関であるかを確認しましょう。個人や知らない団体が情報の発信元の場合は、プロフィールや活動内容を調べて信頼性を判断するのも有効です。
情報が書かれた日付を確認する
情報が書かれた日付を確認し、古い情報や最新でない情報に注意することも対策の一つです。過去の出来事に関する情報は現在と状況が異なっているケースがあるので、情報源の日付を確認して、信憑性を判断しましょう。
一次情報を確かめる
一次情報(公的機関や公式なデータなどから直接提供される信頼性の高い情報))を確かめるのも、フェイクニュースに騙されないための対策になります。フェイクニュースは、一次情報を歪曲、改ざんして作られることが多いため、一次情報を確認することで情報の真偽を判断できる可能性があります。ニュースの情報元となっている記事やデータ、論文などを直接確認することも有効です。
一つの情報だけを鵜呑みにしない
異なる情報源を比較し、一つの情報だけを鵜呑みにしないことも重要です。信頼できるメディアや公的機関、専門家の情報など複数の情報を確認しましょう。本や新聞など、WebサイトやSNS以外の方法で調べることも大切です。
安全なインターネット利用にはセキュリティ対策サービスの活用が大切
前述のような対策を講じていてもフェイクニュースに騙されてしまい、不審なメールに添付されたファイルを開いたり、不正なサイトで個人情報を入力したりしてしまうリスクは残ります。
フェイクニュースは犯罪の手段としても悪用されます。たとえば、受信者の興味や不安な気持ちを悪用したフェイクニュースを含むメールやDM(ダイレクトメッセージ)が届き、本文に記載のURLから不審なサイト(フィッシングサイトなど)に遷移するケースは少なくありません。
フィッシングサイトで個人情報を入力してしまうと、アカウントの不正利用や、金銭的な被害に遭うリスクが想定されます。このような脅威から身を守るためには、セキュリティ対策サービスの活用が大切です。
ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」を活用すれば、インターネット上のさまざまな脅威によるリスクを低減できます。たとえば不審なメールをフィルタリングしてくれる「迷惑メール対策」機能や、閲覧しようとしているサイトが危険なサイトだった場合に警告を表示してくれる「危険サイト対策」機能などが搭載されています。
インターネットを安全に利用するためにも、サービスを活用してセキュリティ対策を万全にしましょう。
まとめ
メディアやブログ、SNSなどで公開される事実ではない情報はフェイクニュースと呼ばれます。近年、ディープフェイクを用いたフェイクニュースが拡散されることが多く、世論などにおよぼす影響も少なくありません。
また、フェイクニュースが掲載されたメールやDMからフィッシングサイトなどの不審なサイトに誘導されて被害に遭うケースもあるため、万全対策を取ることが重要です。
具体的には情報の発信元や日付を確かめたり、複数の情報を比較したりして、フェイクニュースに騙されないようにしましょう。また、不審なメールや危険なサイトを避けることも対策になります。セキュリティ対策サービスも活用して、安全にインターネットを利用しましょう。