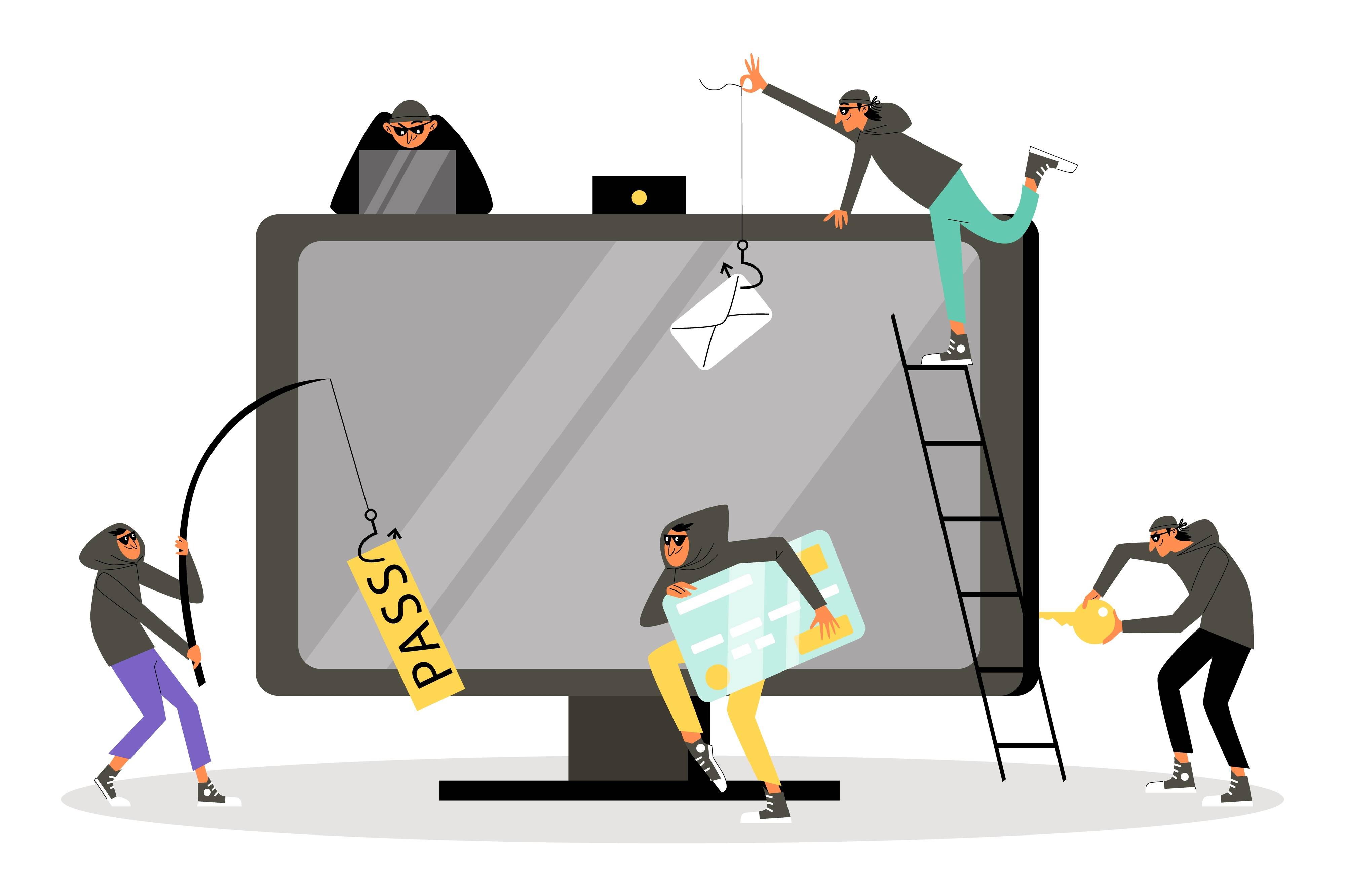AI技術に対するセキュリティ対策とは?具体的なリスクも解説

自動運転や音声認識、データ分析の高度化など、AIの活用はさまざまな分野で進んでいます。一方で、AIを悪用したサイバー攻撃や情報漏洩などの新たなセキュリティリスクも増加傾向にあります。
本記事ではAI技術の進化によって生じる利便性とリスクの両面を解説するとともに、効果的なセキュリティ対策について紹介します。
目次
AI技術によって期待できること
AI技術の進化により、セキュリティ分野においても多くの革新が生まれています。ここでは、具体的なAIの活用例を紹介します。
機械学習によるマルウェアの検出
従来のマルウェア対策ソフトは、あらかじめ登録されたマルウェアの特徴をもとに検出する「シグネチャベース」が主流でした(マルウェアとは、スマホやユーザーに被害をもたらすことを目的とした、悪意のあるソフトウェアのこと)。しかし、シグネチャベースは新しく作られたマルウェアや、改変されたマルウェアを見つけるのが困難です。
AIを活用すれば、マルウェアの動きの特徴を分析し、新しい脅威にも対応できる可能性があります。
ログの監視・解析
AIは大量のログデータを高速に分析し、異常な挙動を自動的に検知することが可能です。たとえば、過去のログデータを解析し、通常のアクセスパターンを学習することで、突発的な異常や通常とは異なるアクセスの発生を素早く察知できるようになります。
また、時間帯ごとのアクセス傾向を分析することで、深夜の不審なログイン試行や特定の時間帯に集中する攻撃の兆候を把握できます。
ネットワークトラフィックの監視・解析
ネットワークトラフィック(ネットワーク上で転送されるデータ量)の監視は、サイバー攻撃を早期に発見するために重要です。不正アクセスの兆候をつかむためには、ネットワークの通信状況を詳しく分析する必要があります。
AIを活用すれば、過去の正常な通信パターンを学習し、違う動きをリアルタイムで検知できます。普段使わないIPアドレスから大量の通信が行われたり、通常とは異なるポート(通信データの通り道のこと)を使ったアクセスが発生したりすると、AIがすぐに異常を察知します。
AI技術の進化によって起こりうる具体的なリスクとは?
AIを悪用した攻撃は日々進化しており、対策を怠れば、知らぬ間に被害に遭ってしまいかねません。
ここでは、AI技術の進化によって起こりうる具体的なリスクをいくつか紹介します。
ディープフェイク
ディープフェイクとは、AIを利用して本物そっくりの偽画像や動画を作成する技術です。特に、顔写真や声をAIで合成し、本人になりすます手口が問題視されています。
たとえば、悪意を持った者ターゲットの顔や声をディープフェイクで再現し、銀行の顔認証システムを突破するといった危険性があります。
不正アクセス
不正アクセスとは、他人のIDやパスワードを盗み、システムに侵入して情報を盗み見たり、改ざん・破壊を行う行為です。これまでもパスワードリスト攻撃や辞書攻撃といった手法が使われてきましたが、AIの進化により、より精度の高い攻撃が可能になっています。
特に悪意を持った者がAIを活用することで、過去のパスワード漏洩データを学習し、ユーザーが設定しそうなパスワードを高い精度で推測することができます。さらに、AIはログイン履歴や行動パターンを分析し、不正アクセスをより巧妙に隠すことも可能です。
そのため、従来のように単純なパスワードを設定していると、簡単に突破されるリスクが高まります。AIを利用した不正アクセスの脅威の増加に伴って、パスワードの強化や多要素認証の設定がこれまで以上に重要になっています。
フィッシングメール
フィッシングメールは、銀行やクレジットカード会社を装った偽のメールを送り、偽サイトにアクセスさせることで個人情報を盗むサイバー攻撃の一種です。従来のフィッシングメールは文法の誤りや不自然な表現が目立つものが多く、注意深い人であれば見分けることができました。
AIを利用すれば正しい文法や自然な言い回しの文章を作成し、正規のメールと見分けがつかないほど精巧な偽メールを作ることが可能です。さらに、個人の趣味嗜好や過去のメールのやりとりを分析し、ターゲットに合わせた内容を作成することもできます。
このようなフィッシングメールは、受信者に疑われることなく開封され、被害が拡大するリスクがあります。AIによってフィッシング詐欺の手口がますます巧妙化しているため、メールの送信元やリンクのURLを細かく確認するなど、慎重な対応が求められています。
AI技術の進化のリスクに備えるためのセキュリティ対策

AI技術の進化により、サイバー攻撃の手法も高度化しています。そのため、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。
ここでは、AI技術の進化に伴うリスクに備えるための具体的なセキュリティ対策について紹介します。
OSやアプリなどを常に最新版にしておく
AI技術の進化により、新たなマルウェアが次々と作られる可能性があります。そのため、基本的なセキュリティ対策として、OSやアプリを常に最新版に保つことが重要です。
サイバー攻撃の手口の一つに、OSやアプリの脆弱性を悪用するものがあります。ソフトウェアの開発元は、脆弱性が発見されるたびに修正プログラムを提供しているため、定期的にアップデートを適用することで攻撃のリスクを軽減できます。
また、自動アップデート機能を有効にしておけば、手動で更新を確認する手間を省きながら、常に最新のセキュリティ環境を維持できます。ウイルスやマルウェアの侵入を防ぐためにも、OSやアプリの更新を怠らないようにしましょう。
複雑なパスワードにしておく
AI技術を悪用してパスワードを解析する手口が増えています。たとえば、過去に流出したパスワードのデータをAIに学習させ、ユーザーが設定しそうなパスワードを予測するケースがあります。そのため、パスワードは推測されにくいものを使用することが重要です。
具体的には、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせたものを設定し、単純な単語や誕生日などを避けるようにしましょう。また、異なるサービスで同じパスワードを使い回さないことも大切です。万が一、1つのパスワードが流出しても、ほかのサービスへの被害が拡大するのを防ぐことができます。安全なパスワードの管理には、パスワードマネージャーの利用も有効です。
二要素認証を導入する
二要素認証は、IDとパスワードに加え、もう一つの要素を使って本人確認を行うセキュリティ対策です。AI技術の発展により、犯罪者はパスワードを予測しやすくなっています。そのため、不正アクセスを防ぐためには、パスワードだけでなく複数の認証方法を組み合わせることが重要です。
一般的には、スマホに送られる認証コードの入力、指紋認証や顔認証などが用いられます。二要素認証を設定することで、パスワードが漏洩しても追加の認証を求められるようになり、不正ログインのリスクを大幅に軽減できます。利便性と安全性を両立させるためにも、二要素認証を活用することが望ましいです。
不審なメールに記載のURLにはアクセスせず、ファイルはダウンロードしない
AI技術の発展により、より巧妙なフィッシングメールが作成されるようになっています。悪意のある者が作成したメールには、不正なサイトへ誘導するURLが含まれていることがあり、アクセスすると個人情報が盗まれる可能性があります。
また、添付ファイルを開くことで、ウイルスに感染するリスクもあります。そのため、送信元が不明なメールや見覚えのないメールは開かないことが重要です。
特にメール本文にURLが記載されている場合は、正規のリンクかどうかを慎重に確認しましょう。文面に違和感がある場合は、メールを削除するのが安全です。こうした対策を習慣化することで、フィッシング詐欺の被害を防ぐことができます。
セキュリティ対策サービスを活用する
どれだけ注意していても、メールフォルダにフィッシングメールが届くと、誤って開いてしまう可能性はゼロではありません。大切なのは、「フィッシングメールをできるだけ開封できないようにすること」です。
セキュリティ対策サービスを導入することで、サイバー攻撃のリスクをさらに低減できます。たとえば、ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「迷惑メール対策」機能は、申し込むだけでフィッシングメールなどの迷惑メールを自動で判別します。
判別された迷惑メールは、専用フォルダに振り分けられるため、誤って開いてしまうリスクを減らすことが可能です。さらに、現在ご利用いただいている迷惑メール対策の設定とも併用できます。
まとめ
AI技術の進化は、私たちの生活を便利にする一方で、新たなセキュリティリスクも生み出しています。ディープフェイクによるなりすまし、不正アクセスの手口の高度化、フィッシングメールの巧妙化など、AIを悪用した脅威が増加しています。こうしたリスクに備えるためには、基本的なセキュリティ対策を徹底することが重要です。
具体的には、OSやアプリを常に最新の状態に保ち、複雑なパスワードを設定することが求められます。さらに、二要素認証を設定し、不審なメールのURLや添付ファイルには慎重に対応することが大切です。また、セキュリティ対策サービスを活用することで、未知の脅威にも対応しやすくなります。AI技術の進化によるリスクを理解し、適切な対策を講じることで、安全にデジタル社会を利用することができるでしょう。