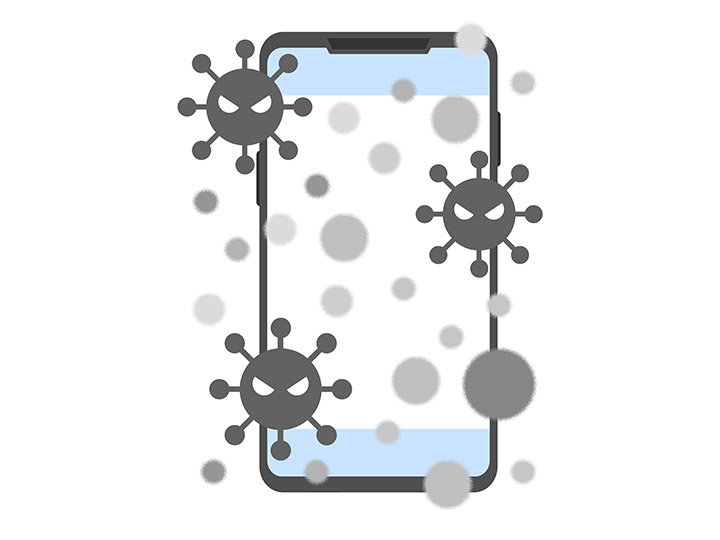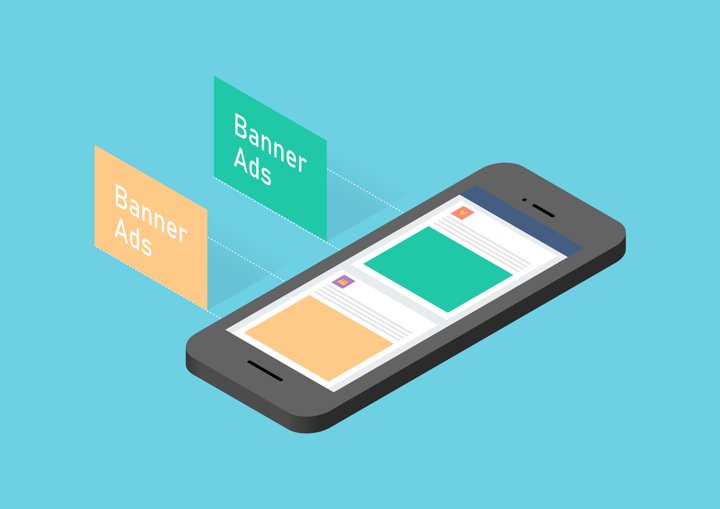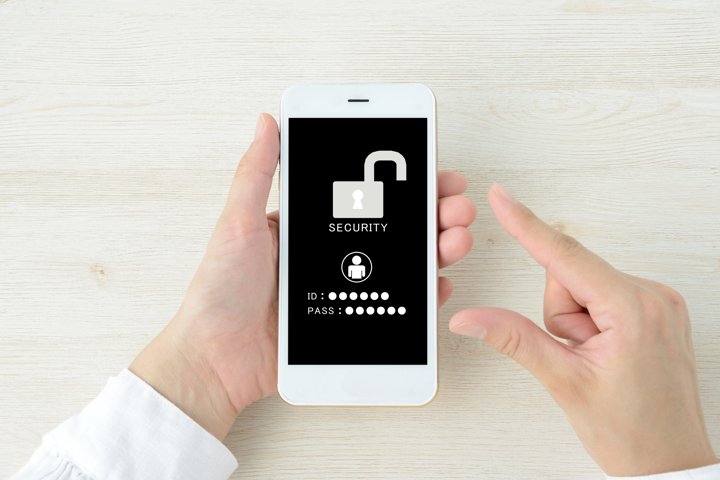ハッキングの仕組みとは?主な被害や未然に防ぐ方法を解説

ハッキングとはコンピューターやネットワークに不正に侵入し、情報を盗んだり、システムを破損したりする行為です。ハッキングを受けると、個人情報の漏洩や金銭的な被害、さらには日常生活や仕事に支障をきたすおそれがあります。
本記事では、ハッキングの仕組みや主な手口を解説するとともに、想定される被害や未然に防ぐための具体的な対策について詳しく説明します。
目次
ハッキングとは

ハッキングとは、コンピューターやネットワークに不正にアクセスし、情報を盗んだり、システムを破損させたりする行為のことです。不正アクセス禁止法などの法律により、ハッキングは多くの場合で違法とされていますが、セキュリティの改善を目的とした合法的なハッキングも存在します。この合法的なハッキングを行う人を「ホワイトハッカー(ホワイトハット・ハッカー)」と呼び、セキュリティ向上のための研究やテストで活躍しています。
一方、違法なハッキングが行われる理由はさまざまで、主に機密情報の窃取や金銭の不正取得、システムの操作権限の確立などが目的です。攻撃者は、セキュリティシステムの脆弱性を悪用したり、人の心理的な隙を突いて騙す手法(ソーシャルエンジニアリング)を使ったりして侵入を試みます。
また、パソコンだけでなく、スマホもハッキングの対象になっています。スマホには、クレジットカード情報や銀行のログイン情報、SNSのパスワードなどが保存されていることが多く、日常生活に深く結びついているため、狙われるリスクが高いのです。スマホがハッキングされると、金融被害やプライバシーの侵害など、生活全般に影響をおよぼす可能性があります。
ハッキングの仕組みとは
攻撃者はまず、ターゲットとするパソコンやスマホが使用しているアプリやシステム、ネットワークの構成を調査します。調査の目的は、セキュリティの弱点、つまり脆弱性を見つけ出すことです。脆弱性が特定されると、そこを入り口としてシステムへの侵入を試みます。
たとえば、パソコンの場合は、古いソフトウェアや未更新のセキュリティ設定が脆弱性として狙われることがあります。攻撃者はこの弱点を利用して、ターゲットのシステムにアクセスするのです。侵入に成功すると、システム内のデータを盗む、不正なプログラムを仕込む、システムそのものを操作不能にするなど、攻撃を実行します。
一方、スマホがハッキングされる場合には、不正なアプリをインストールさせたり、フィッシング詐欺のリンクにアクセスさせたりするなど、ユーザーの行動を利用する手口がよく用いられます。たとえば、不審なリンクを含むメールやメッセージを送り、そのリンクにアクセスさせることでデバイスをマルウェア(スマホやユーザーに被害をもたらすことを目的とした、悪意のあるソフトウェア)に感染させ、個人情報を抜き取る方法です。
ハッキングの主な手口

ここでは、ハッキングの代表的な手口を6つ紹介します。
マルウェア
マルウェアの主な手口は、デバイスへの不正な侵入や乗っ取り、データの破壊・改ざんなどです。具体的には、個人情報の窃取やデータ破損、意図しないメールの送信など、多岐にわたる被害が発生します。
主な感染経路は、不正なメールやWebサイトです。ユーザーが不正なメールの添付ファイルを開いたり、悪意のあるWeb広告にアクセスしたりすることで、マルウェアがデバイスに侵入します。
マルウェアの種類として、データを暗号化して身代金を要求するランサムウェアや、個人情報を密かに盗むスパイウェアなどが代表的です。見た目が通常のソフトウェアと区別しづらいため、セキュリティアプリやソフトを常に最新の状態に保つことが重要です。
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃は、ソフトウェアやOSの脆弱性が修正される前に、その脆弱性を突いて不正アクセスを行う手口です。主にパソコンのOSや企業が利用する業務アプリケーションを対象に行われます。
ゼロデイ攻撃では、脆弱性が発見され、修正プログラム(パッチ)が提供される前の短期間を狙い、悪意あるコードを注入してシステムに侵入します。たとえば、修正プログラムが未適用の業務管理システムに攻撃が行われ、内部データが盗まれるケースが代表的です。
ゼロデイ攻撃を防ぐには、ソフトウェアの更新を怠らず、脆弱性情報を確認して迅速に対応することが欠かせません。
総当たり攻撃(ブルートフォースアタック)
総当たり攻撃とは、考え得るすべての文字列の組み合わせを試し、パスワードを解読する手口です。主にパソコンやスマホのログインシステムやオンラインサービスのアカウントを対象に行われます。
たとえば、4桁の数字で構成されたパスワードであれば、「0000」から「9999」までの10,000通りを自動的に試すことで突破を試みるのです。単純なパスワードや短いパスワードは簡単に突破されるリスクが高いため、英字の大文字と小文字、数字、記号を組み合わせた長く複雑なパスワードを設定することが重要です。
データベースを不正操作するハッキング(SQLインジェクション)
データベースを不正操作するハッキングは「SQLインジェクション」とも呼ばれ、主にパソコンを対象とするハッキング手法です。Webサイトやアプリケーションのセキュリティホール(設計上の欠陥や設定ミス)を利用して、不正なSQL文を入力し、データベースを操作します。SQLとは、データベースを操作するための言語のことです。
たとえば、ログイン画面や問い合わせフォームで入力内容を正しく検証しない場合、攻撃者は不正なSQL文を注入し、保存されている個人情報を盗んだり、データを改ざんしたりすることが可能です。
セキュリティホールはハッキングの入り口となるため、脆弱性を早期に発見し、修正プログラムを適用することが重要です。
ソーシャルエンジニアリング
ソーシャルエンジニアリングは、人間の心理的な隙や行動の癖を悪用して、個人情報を騙し取る手口です。技術的なハッキングではなく、主に電話や対面で情報を聞き出すといったアナログな方法を使用する点が特徴です。
たとえば、攻撃者が企業のIT担当者を装い、従業員に電話をかけてパスワードを聞き出すケースがあります。また、ゴミ箱に捨てられた書類から機密情報を収集する「トラッシング」や、キーボードやスマホの入力操作を覗き見る「ショルダーハッキング」も含まれます。
また、攻撃者は巧妙な話術で被害者との信頼関係を築き、直接マルウェアを送り込んだり、偽のWebサイトに誘導して情報を入力させたりするケースもあります。
ソーシャルエンジニアリングを防ぐには、個人でも企業でも、情報管理の徹底と警戒心を持つことが重要です。個人情報を不用意に公開しないことはもちろん、不審な電話やメールに注意を払いましょう。ソーシャルエンジニアリングについては、こちらの記事でも解説しているのでぜひご覧ください。
ソーシャルエンジニアリングとは?代表的な手法や具体的な対策を紹介
フィッシング
フィッシングとは、偽のWebサイトやメール、SMSを利用してユーザーを騙し、個人情報を不正に取得する詐欺手法です。パソコンだけでなく、スマホも標的となり、ブラウザやメールを介して被害が広がる可能性があります。
たとえば、「アカウントがロックされました」という偽メールでユーザーを誘導し、偽のログインページにIDやパスワードを入力させる手口が挙げられます。IDやパスワードを入力してしまうと、その情報は攻撃者に送信され、個人情報の窃取や不正利用といったさらなる被害につながりかねません。
フィッシングの被害に遭わないためにも、メールやメッセージ内のリンクにアクセスする前に送信元のアドレスやURLを慎重に確認してください。不審な点があればアクセスを避け、公式のWebサイトやアプリを直接開くことを心がけましょう。
ハッキングにより想定される主な被害とは
ハッキング被害の種類は多岐にわたりますが、ここでは特に深刻な影響をおよぼす3つの被害について解説します。
個人情報などの大切なデータが盗まれる
ハッキングによってパソコンやスマホに保存されている重要なデータが盗まれると、情報が悪用されるリスクが高まります。特に名前や住所、電話番号などの個人情報が漏洩した場合、被害は深刻化する可能性があるでしょう。
たとえば、漏洩した個人情報が詐欺グループにわたると、架空請求やなりすまし詐欺に利用されるケースがあります。また、ハッカーによって盗まれたデータがインターネット上で売買されることもあり、情報が広く拡散されてしまう危険性も考えられるでしょう。
クレジットカードなどを不正利用される
ハッキングによってクレジットカード情報が盗まれると、知らない間に不正利用され、金銭的な被害に直結するリスクが高まります。たとえば、盗まれた情報を用いて商品が購入されたり、送金が行われたりすることで、被害者に大きな経済的損失を与える可能性があるのです。
また、盗まれたカード情報は、ダークウェブと呼ばれるインターネットの一部で売買されることがあり、さらに多くの犯罪に利用されるケースもあります。
第三者になりすまされ、家族や知人に被害がおよぶ
ハッキングによって盗まれた個人情報が悪用されると、攻撃者が被害者になりすまし、家族や知人に新たな被害をおよぼす危険があります。
たとえば、ハッカーが被害者のメールアドレスや電話番号を利用して知人に連絡を取り、偽の緊急事態を装ってお金を騙し取るといった手口があります。また、SNSアカウントを乗っ取られ、詐欺を目的としたメッセージを送信されたり、不審なリンクを拡散されたりするケースも考えられるでしょう。
ハッキングを未然に防ぐための対策
ハッキングから身を守るためには、日常的な注意と適切な対策が欠かせません。具体的な対策方法を3つ紹介します。
セキュリティ対策サービスを活用する
セキュリティ対策サービスの活用は、ハッキングを防ぐ有効な手段です。スマホがウイルスに感染すると、個人情報が盗まれるリスクが大幅に高まります。そのため、ウイルスの有無を定期的にチェックするのがおすすめです。
ドコモの「あんしんセキュリティ スタンダードプラン」の「ウイルス対策」機能では、スマホやタブレット本体、アプリ、外部メモリにウイルスがないかスキャンでき、検知された場合には即座に通知を受けられます。
OSとソフトウェアを常に最新の状態に保つ
OSやソフトウェアの更新は、ハッキングを防ぐ上で基本的な対策です。システムに脆弱性(セキュリティ上の欠陥)が見つかると、それを放置することでハッカーに悪用されるリスクが高まります。しかし、定期的にアップデートを行えば、脆弱性を修正し、攻撃を防ぐことが可能です。
更新を確実に行うためには、自動更新機能を有効にするのがおすすめです。自動更新を利用すると、OSやソフトウェアを常に最新の状態に維持できます。日頃からアップデートの確認・更新を心がけ、安全な環境を構築しましょう。
複雑なパスワードを設定する
ハッキングを防ぐ基本は、強固なパスワードを設定することです。簡単に推測されるパスワードでは、ハッカーに突破されるリスクが高まります。たとえば「12345」や「password」などの単純な文字列や一般的な単語は避けましょう。
安全なパスワードを設定するには、大文字、小文字、数字を組み合わせた文字列を使い、できるだけ長くすることが有効です。より複雑な形式を採用することで、強固なセキュリティを実現できます。
多要素認証を設定する
多要素認証は、セキュリティを強化するための有効な手段です。パスワードだけでなく、SMSで送られる確認コードや指紋認証など、複数の認証方法を組み合わせることで、アカウントへの不正アクセスを防ぎやすくなります。
たとえば、ログイン時にIDとパスワードを入力したあと、スマホに届くコードを入力する仕組みを追加することで、より安全に認証できます。一つの認証方法が破られても、別の方法でブロックできるため、ハッキングされる可能性を大幅に下げられるのです。
不審なメールに記載されているURLにアクセスしない
メールを使ったハッキングも広く行われているため、不審なメールには注意が必要です。本文に記載されたURLにアクセスすると、ウイルスに感染したり、個人情報を盗まれたりするおそれがあります。
たとえば、件名に不自然な日本語表現が含まれるメールや、差出人が不明なメールは、迷惑メールの可能性が高いといえます。不審なメールを受け取った場合は、開封せずに削除することが安全です。
フリーWi-Fiを安易に利用しない
フリーWi-Fiは便利ですが、セキュリティが十分でない場合が多く、ハッキングのリスクを伴います。たとえば、暗号化されていないフリーWi-Fiでは通信内容が盗み見られる可能性があり、オンラインバンキングの利用やショッピングを行う際は特に危険です。
こうしたリスクを回避するために、公共のWi-Fiでは重要な操作を控え、信頼できるWi-Fi環境で作業することを心がけましょう。
まとめ
ハッキングは、パソコンやスマホを標的に情報を盗む、システムを操作不能にするといった被害を引き起こす深刻な脅威です。攻撃者はマルウェアを仕込んだ不正なアプリやサイトを用いて、個人情報を盗み出したり不正操作を行ったりします。
ハッキング被害を防ぐには、セキュリティ対策サービスを活用し、OSやソフトウェアを最新の状態に保つことが効果的です。また、強固なパスワードの設定や多要素認証の設定により、アカウントの安全性を高められます。
デジタル社会における安全を守るためには、セキュリティ意識を持ち、適切な対策を講じることが重要です。日頃から予防策を徹底し、あんしんしてインターネットを利用できる環境を整えましょう。